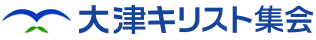聖書メッセージ17「夏目漱石の問い」
第17回「夏目漱石の問い – 人はどこからきてどこにいくのか?」

この問題についてパスカルは、『パンセ』の中で、こう言っています。
「私は、だれが一体私をこの世に置いたのか、この世は何であるのか、私自身が何であるかはわからない。私はすべてのことについて、恐ろしい無知の中にある。私が知っているすべてのことは、私がやがて、死ななければならないことであり、しかし、どうしても避けることのできないことであり、しかしどうしても避けることのできない死こそ、私の最も知らないことである。私はどこから来たのか知らないと同様に、どこへいくかも知らない。」
人間はどこから来て、どこに行くのか、この問題は人間の経験や理性によっては解答することはできません。断言できないのです。しかし、神の言葉である聖書はこの難問について明確な答えを示しています。
まず私たちは、どこから来たのでしょうか? 生命の誕生は、卵子と精子が結合し、受精卵になり、それが細胞分裂を繰り返して、人のからだが形成されていきます。しかし、そこには神の御手があり、一人一人が命を与えられて、この世界に誕生してくるのです。偶然に私が生じたのではなくて、自然科学的な生命の誕生のプロセスを経つつも、その背後に神の御手と意志があって、生まれてくるのです。
聖書には、“神はすべての人に、いのちと息と万物とをお与えになった方」(使徒の働き、17:25)と記されてあり、また神について、「あなたを母の胎で形造った方」(イザヤ書、44:24)と書かれてあります。私たちは、神によって命を与えられ、神によって創造されたというメッセージです。
それでは次の問いに移りましょう。私たちはどこに行くのでしょうか?
多くの人は人生は死で終わりと考えています。死によってすべてが終わりであれば、人生はできるだけ楽しく、快楽を追求しようと考えるのが自然です。限りがある人生の中で、“楽しめ、歌え、踊れ”という刹那的な生き方になります。。また死ですべてが終わりであれば、厭世的な生き方も生まれてきます。どんなに努力しても、死によって今まで積み重ねてきた努力と成果がガタガタと音を立てて崩れていくという絶望感と虚しさが私たちのこころを浸食するのです。
漱石は、1911年11月の五女ひなこ(1歳8か月)の死に際して、大きな衝撃を受けました。彼は、「昨日は、葬式、今日は骨上げ、明後日はもしかすると待夜である。多忙である。然しすべての努力をした後で考えると、すべての努力が無駄になる。死を生に変化させる努力でなければすべてが無益である。」とその苦しみを吐露しています。彼が44歳の時です。
しかし、聖書は人生は死で終わるものではないと語っています。その後に分岐点があり、一つは永遠の滅びに至る道であり、もう一つは永遠のいのち、天国に至る道です。では、どうしたら、人間は、永遠のいのちを受け、天国に入ることができるでしょうか?誰でも死んだ後、自動的に天国に入ることができるわけではありません。この二つの道を分かつ基準は、私たちに人生の総決算を求める全能の神の前に罪が赦されているかどうかです。それでは、どうしたら、裁判官である神の前に私たちの罪は赦されるのでしょうか。罪が赦され、無罪判決を受ける方法が一つだけあります。聖書は、私たちの罪のすべてを負って神の子であるイエス・キリストが十字架で身代わりに神の裁きをうけてくださった、そのイエス・キリストを救い主として信じる信仰によって、罪赦され、永遠のいのちが与えられると記しています。
「神は、実に、その一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つためです。」(ヨハネ3:16)
死を超えた希望があるからこそ、この地上の生を絶望せずに、期待しつつ生きることができます。漱石が求めた「死を生に変化させる努力」は、イエス・キリストの十字架において完成したのです。聖書は「死は勝利に呑み込まれた。死よ、おまえの勝利はどこにあるのか、死よ、おまえのどげはどこにあるのか。—-神はわたしたちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えて下さいました。」(Ⅰコリント15:54,57)と宣言しています。
最初の問いに戻りたいと思います。人はどこからきてどこに行くのか? 漱石は「答えよ」と、心の中から絞り出すように叫びました。聖書は、人のいのちは神によって与えられ、神から来ること、そして神から離れ、神に背を向けてきた人間は、イエス・キリストの十字架の犠牲が自分のためであったと信じる信仰によって、罪赦され、永遠のいのちを与えられると約束するのです。なんとすばらしいメッセージではないでしょうか。漱石がこの真理を知っていたならばと残念に思わざるをえません。
大津集会では、人生の諸問題について、聖書からわかりやすく学んでいま す。気軽に教会の門を叩いてください。心から歓迎いたします。
文責 古賀敬太