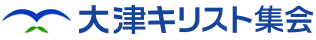聖書メッセージ06「芥川龍之介と聖書」
第6回「芥川龍之介と聖書」

文豪芥川龍之介(1892~1927,享年36歳)が自殺した自宅には、一冊の聖書が残されてありました。彼は自殺する直前に、「西方の人」、「続西方の人」という短編を書きました。芥川は、1927年7月24日に自殺しますが、「西方の人」を書いたのが7月10日、「続西方の人」は、死の前日の7月23日です。「西方の人」とは、イエス・キリストのことを意味します。彼が、死の直前、イエス・キリストのことを考えていたことは間違いがありません。彼は、必死で光を求めていました。その証拠に「西方の人」には、「我々は、エマオの旅人たちのように我々の心を燃え上がらせるキリストを求めざるをえないであろう。」、また「私は、四福音書の中にまざまざと私によびかけているキリストの姿を感じている。私のキリストを描き加えるのも私自身にはやめることはできない。」とまで書き記しています。「キリストを求める」、「私に呼びかけているキリストの姿」とは、重い言葉で、芥川の心の奥深くの心の葛藤を示しています。しかし、結果として、芥川はキリストを求めながら、キリストを信じることなく、自殺の道を選択してしまいました。闇の中から光を求めながら、光に出会うことはありませんでした。なぜでしょうか。?
晩年もっとも聖書に近づいた芥川はなぜ、破滅の道を選択したのでしょうか。芥川がやはり自殺の数週間前に書いたといわれる短編「歯車」の中にそのヒントがあります。重要な個所ですので、関係する箇所を一部引用いたします。
「僕は、地下室を抜けて往来へ出て、ある老人を訪ねることにした。彼はある聖書会社の屋根裏にたった一人こずかいをしながら、祈祷や読書に精進していた。僕らは、火鉢に手をかざしながら、壁にかけた十字架の下にいろいろのことを話し合った。なぜ、僕の母は発狂したのか?なぜ僕の父は事業に失敗したのか?
なぜ、僕は罰せられたのか?」—–「中略」
「信者になる気はありませんか。」
「もし僕にでもなれるものなら——」
「何もむずかしいことはないのです。ただ神を信じ、神の子のキリストを信じ、キリストの行った奇跡を信じさえすれば——」
「悪魔を信じることはできますがね。—–」
「なぜ、神を信じないのです?もし影を信じるならば、光を信じずにはおられないでしょう。?」
「しかし、光のない暗闇もあるでしょう」
「光のない暗闇とは?」
僕は黙るより外はなかった。彼もまた僕のように暗闇の中を歩いていた。が、暗闇のある以上は、光もあると信じていた。僕らの論理の異なるのは、唯こういう一点だけであった。しかし、それは、少なくとも越えられない溝に違いなかった。 「けれども光は必ずあるのです。」
実は芥川には、彼のために祈り、彼にイエス・キリストの救いを伝えていた室賀文武という内村鑑三の弟子で熱心なクリスチャンがいました。芥川が救われることを祈り続けてきた人物です。芥川の日記には、「昭和2年7月14日、室賀文武が訪ねてきて、深夜までキリスト教について話す。」と記されてあります。自殺する10日前のことです。
「歯車」を読むと、闇の中に輝いている光であるイエス・キリストを信じる老人と、闇から脱しようともがきながらも、光の存在を信じることができない芥川との「越えられない溝」が手にとるように伝わってきます。
しかし、なぜ芥川は光であるイエス・キリストを求めながら、暗闇の中に留まってしまったのでしょうか?室賀は、「西方の人」を読んで失望したと言われています。というのも、芥川は、自分の人生をキリストに投影し、「神の子」イエス・キリストではなく、「人間イエス」を描いたからです。イエスの十字架の死も、私たちの罪を赦すための身代わりの死ではなく、「人間イエスの悲劇的な死」で、自らもそこに向かおうとする人生の絶望的な最後を見たにすぎません。芥川は、「遺書」の中で、「僕は、過去の生活の総決算のために自殺するのである。」と書いていますが、彼は文豪としては成功を博しましたが、一人の人間としては、人間の罪の現実という暗闇に圧倒されてしまいました。
しかし、聖書は私たちに語ります。神の子イエス・キリストは、十字架上で私たちの罪のために死なれただけではなく、三日目に墓を打ち破って、よみがえられ、今も生きておられると。そしてイエス・キリストを信じる人を暗闇から光へと移してくださる方であると。死を超えた希望があると。
「私は、世の光です。私に従うものは、決して闇の中を歩むことがなく、いのちの光を持つのです。」(ヨハネ8:12)
大津キリスト集会は、疲れている人、重荷を負っている人、真理を求めている人が、教会のドアを勇気を持ってノックされることを心から歓迎いたします。