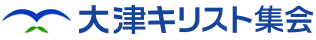第9回 「聖書入門ーキーワードで読む」
第九回 贖い(λὐτρωσις(リュートローシス),άπολύτρωσις(アポリュトローシス)、Redemption)
「贖いのギリシャ語と本来的意味」
聖書で「贖(あがな)う」という場合には、代価を払って買い取る、ないし解放するという意味があります。奴隷解放が、イメージとしてわかりやすいと思います。奴隷を主人から、身代金を払って解放するという意味です。
もちろん私たちは奴隷ではなく、自由人です。自分の選択や決断によって行動することができます。しかし聖書は、人間がいかに弱く、本能や欲望によって駆り立てられる存在であるかを示しています。とくに日本では、女性の盗撮をはじめ性的な被害が多発し、止まるところをしりません。政治家、高級官僚、教育者、警察官、会社員、大学生の性的な犯罪が話題にならない日はないほどです。理性も道徳も、面子も、性的衝動をコントロールできない程度にエスカレートしています。このことを聖書は、罪の奴隷と言っています。そのような罪の奴隷である私たちが、イエス・キリストの十字架の犠牲という代価が支払われて、罪の奴隷から解放され、真に自由とされることを贖いと言言います。
ギリシャ語のλὐτρωσις(リュトロオーシス)が贖うという名詞で、3回用いられ、リュトローマイが贖いを意味する動詞で3回用いられています。英語では、redemptionです。またリュローシスが強い意味を持つと、άπολύτρωσις(アポリュトローシス)という言葉が用いられます。これは、新約聖書で10回用いられ、身代金の支払いによってなされる解放、奴隷の買い戻しを意味します。
例えば、「神の恵みにより、キリスト・イエスによる贖いを通して、値なしに義とさ認められるからです。」(ローマ3;24)の贖いにはアポリュトローシスが用いられています。
またコロサイ書の1:14節には、「この御子にあって、私たちは贖い、すなわち罪のゆるしを得ているのです。」とありますが、この贖いが、アポリュトローシスです。また贖う(アポリュオー)の動詞は、新約聖書で69回使用されています。
「奴隷からの解放」
奴隷という言葉は現在の自由な社会においては、違和感があるかもしれません。しかし人間は罪の奴隷です。罪によって縛られた無力な存在です。聖書の救いは、罪の奴隷から、キリストの奴隷へと主権が転換することを言います。聖書には、「御父は、私たちを暗闇の力から救い出して、愛する神の御支配の中に移してくださいました。」(コロサイ1:14)とあります。
「旧約聖書における贖い」
旧約聖書も、出エジプトにおけるユダヤ人の解放を、「贖い」という言葉で表現しています。
「わたしは主である。私はあなた方をエジプト の苦役から連れ出し、労役から救い出す。伸ばした腕と大いなるさばきによってあなた方を贖う。私はあなた方を取ってわたしの民とし、わたしはあなた方の神となる。」(出エジプト6:6〜9)
ここでも主権の転換、解放の意味内容が示されています。またイザヤ書において神はユダヤ人のバビロン捕囚からの解放を念頭において、「恐れるな。わたしがあなたを贖ったのだ。わたしはあなたの名を呼んだ。あなたはわたしのもの。」(イザヤ43:1)と語られています。
ここで新約聖書の贖いについて大事なポイントを4点見てみましょう。
【第一のポイントー 贖いと償いとは異なる】
第1のポイントは、日本の日常語では、贖いという言葉は使わないので、償いと間違えてしまう方も少なからずおられます。償いとは罪を赦してもらうために何かをすることですが、贖いは、一方的な神の恵みにより、罪の奴隷から解放されることです。自分の力でどんなに頑張っても罪の支配から自分で自分を解放することはできません。
【第二のポイントー贖いは罪の赦しを含む】
第二のポイントは、贖いは、救いの文脈で用いられる場合、罪からの解放と同時に、罪の赦しを含んでいるということです。「この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の赦しを受けているのです。」(コロサイ1:14)とあります。
【第三のポイントーイエス・キリストの血という代価の必要性】
贖いの第三のポイントとして、罪の奴隷から解放されるためには、「身代金」、「代価」が支払われる必要があります。代価が支払われることなくして、罪の赦し、そして罪からの解放はありません。「あなた方は、代価を払って買い取られたのです。(1コリント6:20) とある通りです。そしてその代価とはイエス・キリストの血です。
「ご承知のように、あなた方が先祖から伝わったむなしい生き方から解放されたの
は、銀や 金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリ
ストの、尊い血によったのです。」(1ペテロ1:18〜19)
私たちの罪が赦され、罪から解放されるために支払われた代価は、全く罪のない神の子イエス・キリストです。神は、独り子イエス・キリストを十字架につけるほどに私たち一人一人を愛してくださいました。いかに神が私たちを高価で尊いものとみなしておられるかの証明です。わたしたちは、自分にとって価値がないと思えるものには一銭もお金を使いたくありませんが、ものすごく価値あるものには、たとえ高額なお金を支払っても、また借金をしてでも購入するのではないでしょうか。同じように、神は独り子イエス・キリストを代価として支払うほどに、私たちを愛しておられます。
「第四のポイントー身体の贖い」
贖いの第四のポイントは、贖いが未来の意味において使用されている点です。聖書は、魂の救いという意味で「贖い」という言葉を使っていると同時に、将来イエス・キリストの再臨の時に、死者が復活し、朽ちない栄光の身体に変えられるという肉体的な意味でも「贖い」という言葉を用いています。パウロは、そのことをうめきつつ待ち望んでいました。
「そればかりではなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、心の中でうめき
ながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちのからだの贖われることを待ち
望んでいます。」(ローマ書8:23)
主イエスが再び来られる時に、信者がよみがえり、罪のない栄光の身体に一瞬にして変えられることが、パウロだけではなく、すべてのクリスチャンの望みなのです。
「贖い」が代表的な事例ですが、聖書を読む時に、キーワードの意味を理解しておけば、聖書がもっと身近で、わかりやすいものとなります。是非救いの理解にとって最も大事な「贖い」の意味を理解してください。