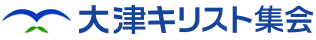聖書メッセージ40
ゼーレン・キルケゴール(1813〜1855)と聖書
「思想家キルケゴール」

今日は、少し難しくなりますが、19世紀のキリスト教思想家であるゼーレン・キルケゴールについて一緒に考えたいと思います。彼はデンマークのコペンハーゲンに生まれ、42 歳の生涯を生き、日本の知識人にも甚大な影響を及ぼしました。彼は 人間の絶望や苦しみを神との関係において鮮やかに描き出しており、彼の著作を読むと、人生に対する決断を迫られる厳粛な思いに導かれ、背筋がピンとする経験をします。ここでは、キルケゴールの生涯の特徴を三点、ご紹介したいと思います。
「あれか、これか」
キルケゴールの生涯の第一の特徴は、「あれか、これか」であって、いくつかの選択肢の中で、一つのものを選びとっていく生涯です。「あれも、これも」で、多くのものを付け加えて、自分を肥え太らせていく歩みではなくて、一つのものに専心し、他のものは捨てていく生涯でした。その一つのものこそ、キルケゴールにとってイエス・キリストでした。
「単独者」
第二の特徴は、「単独者」ということを強調したことです。これは、わかりやすく言えば、神の前に一人立つということです。キルケゴールは、多数や世論に追随し、自己を見失うことを批判します。日本人は、「赤信号 皆でわたれば怖くない」、「バスに乗り遅れるな」、「和をもって尊しとすべき」、「空気を読みなさい」、「長いものに巻かれろ」という言葉に象徴されているように、行動の基準がいつも、多数者やその時々の勢い、あるいは権力者なのです。日本人は、他人と異なった意見を持ち、行動することを極端に嫌うのです。実はこうした格言は、日本人の国民性に深く根ざしている考え方や行動様式を表現しているものです。そこでは、「単独者」というのは孤独、孤立、見捨てられていることを意味するマイナス概念でしかありません。しかしどんなに友人や家族の絆があったとしても、人間は最終的に自己の決断で生き、また死に、神の前に一人立たなければならないのではないでしょうか。
「死に至る病」
第三番目のキルケゴールの特徴は、人間と神との関係、そして神の前における罪の問題を徹底して、真剣に考え抜いたことです。彼が婚約者レギーネ・オルセンとの婚約を破棄したことも、このことと関係があります。ここでは、彼の主著の『死に至る病』(1849)を取り挙げてみたいと思います。この書物は彼の主著であり、岩波文庫で簡単に入手できます。私は、有志の学生と一緒に古典を読む会を持っており、今までアウグスチヌスの『告白』、パスカルの『パンセ』、ドストエフスキーの『罪と罰』、キルケゴールの『死に至る病』などを読んできました。特に『死に至る病』は、難解な概念が出てくるので、理解するのに時間がかかりました。しかし、そこに秘められたメッセージは極めて単純であり、聖書が理解できれば、十分に理解できるものなのです。一言で言うと、救い主イエス・キリストの招きにしたがって、「あなたの創造者である、神に帰りなさい」というメッセージなのです。
キルケゴールが「死に至る病」という時に、それは「絶望」を意味しています。そして絶望とは、苦しんでいる、希望が見出し得ないという主観的な感情や状態ではなく、創造者である神から切り離されているという存在の状態を示しています。人間が神から離れ、神を見失っている状態、もっと言えば本来の人間のあり方から遠く隔たっている状態です。
聖書ではそれを罪と言います。創造者である神は、人に命を与え、生かし、愛しておられる存在です。問題は、その神から切り離されている、神に背を向けて自己中心的な生活をしてい ることが、聖書で言っている罪なのです。ここでは、「死に至る病」=絶望= 神に背を向けていること= 罪(ギリシャ語ではハマルチアで、的外れの意味)という等式が成り立ちます。
「二種類の絶望している人」
キルケゴールは、絶望している人には、二種類あると言います。神から離れていることを自覚している人と、自覚していない人です。キルケゴールは後者の人々を「絶望の中でも最も絶望している人」と言っています。最も深刻な絶望は、自分が絶望状態にあることを知らないことであり、あたかも神が存在しないことが当たり前のように生活していることです。そこでは、神を持ち出すことさえ拒否的であり、神の存在が完全に忘れられています。自分が病気であることを自覚すれば病院に行き、治療をうけて、回復できますが、病気なのに、そのことを認めず、放置すれば、死に至る病となるのです。肉体の病気の場合は肉体の死ですが、神から切り離されているという病気は、それにきずかず、治療しなければ、永遠の死に至るのです。これこそ「死に至る病」の本来的な意味なのです。
「間違った三つの解決策」
しかし、神から離れていることを自覚し、Uターンして神に帰る必要性を理解している人にも、その切り離されている状態にとどまる人と、罪赦されて、神に帰る人がいます。とどまり、神に帰ろうとしない人には三つのパターンがあります。
第一のパターンは、神に帰ることは、自分を中心とした生活から神を中心とした生活に転回することなので、自分がしたいことができないので、神に帰ることを拒否、ないし逡巡する人々です。神を信じると、自分の自由が束縛されると考えるのです。近代には太陽が地球を回っているという天動説から地球が太陽を回っている地動説へと「コペルニクス的転回」が行われましたが、当時はその事実を認めようとしない人が多かったのです。自己中心的な人生観から神中心の人生観や世界観への転回に対しても同様です。
第二のパターンは、神に帰る方法として、自分の行いを積み重ねて、聖い神に下から近づこうとすることです。例えば、マルテイン・ルターは、神に受け入れられるために、善行、断食、祈祷を行い、一所懸命苦行しましたが、すればするほど、自分の醜さがあぶり出されて、絶望してしまいました。彼は自分の良い行いによって神に受け入れられられようとしましたが、無駄でした。しかし、最終的に自分のために十字架にかかり死んでくださったイエス・キリストを信じる信仰によって、罪赦されて、平安が与えられます。あくまでも自分の行いに固執して、キリストの十字架における罪の赦しを信じなければ、絶望的状態が続くのです。それはいまだ自分というものに固執している姿なのです。
第三のパターンは、極端ですが、ニーチェのように、自分が神から離れていることを意識しつつも、神に帰るのではなく、神の存在そのものを否定して、自分を「超人」、つまり自分を神の座におく道です。彼はその戦いに全精力を注ぎ出し、あげくのはてに発狂してしまいました。聖書が言っている根本的な罪は高慢であり、結局は自分を神の立場に置くことなのです。それは神の前にへりくだることとは正反対の態度です。聖書には、「神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを与えられる」とあります。
「正しい解決策」
キルケゴールが望む解決策は、自分の罪を告白して、イエス・キリストを救い主として信じて、神に帰る道です。またこれこそ、神が望んでおられることです。ルカの福音書一五章に「放蕩息子」の話が出てきますが、父親に反逆した次男が自分の罪を悔い改めて、父親のもとに帰るシーンです。その時、父親が迎えに出て、帰ってきた子供を抱擁し、大喜びで迎えるのです。神は、ひとり子である罪のないイエス・キリストの十字架の死を通して、私たちの罪を赦し、神に帰る道を開いてくださいました。キルケゴールは、イエスをこよなく愛しました。それは彼がイエスの絶大なる価値を知っていたからであり、イエスの十字架の死と復活を通して、生ける神に帰ることができることを理解していたからです。
「キルケゴールの回心」
キルケゴールは、『死にいたる病』の前年、1948年に回心を経験しますが、4月19日の日記にその回心について、「私の存在全体は変革された。私の隠蔽性と閉じこもりは破られた。偉大なる神よ、恵みを与えてください!」と書き記しています。「隠蔽性や閉じこもり」とは、キルケゴールによれば、「ただ自己自身のいうことだけに耳を傾け、ただ自己自身だけを問題にして、自己自身に閉じこもっている」状態ですが、回心とは、それが破られ、神の恩寵 にすがり、へりくだって、イエス・キリストの十字架における罪の赦しを心から受け入れることを意味しているのです。
キルケゴールは、1935年の手記の中で、「私にとって真理であるような真理を発見し、私がその為に生き、そして死ぬ事を願うようなイデーを発見することが重要である」と書き記しています。そして彼は約九年後にこの真理をイエス・キリストに見出し、イエス・キリストに徹底して従う生涯を選び取るのです。
「イエス・キリスト」
ドフトエフスキー、パスカル、キルケゴールは、イエス・キリストに心を動かされた人々でした。ドストエフスキーは、聖書をむさぼり読んでいたシベリアのオムスクから、ある婦人に宛てた手紙の中で、逆説的な表現ですが、「もし誰かが自分に、キリストは真理の枠外に立っていることを示し、またもし真理が本当にキリストの外にあるならば、僕は真理のところに留まるよりは、キリストの所に留まる方が良い」と自己の率直な思いを伝えています。またパスカルは、『パンセ』の中で、「我々は、イエス・キリストによってのみ神を知る。この仲介者がいなければ、神との交わりはすべて取り去られる。—-私たちは、イエス・キリストによってのみ、生と死を知る。イエス・キリストを離れて、我々は我々の生、我々の死、我々の神、我々自身が何であるかを知らない」と告白しています。
皆さんも、聖書を通して、イエス・キリストを求めて見られませんか。大津集会は、皆様のご来訪を心から歓迎いたします。
参考文献 キルケゴール『死に至る病』(岩波文庫)
古賀敬太『西洋政治思想と宗教』(風行社、2018年)