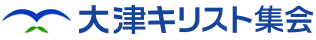第34回 からだ(body,ϛῶμα, ソーマ)
第34回 からだ(body,ϛῶμα, ソーマ)
ソーマ(ϛῶμα)という言葉は新約聖書で142回用いられています。その用い方を三つのポイントで考えてみたいと思います。
第一は、人間の構成要素に関してです。聖書には、人の構成要素として、霊(πννεῦ μα,プネウマ)、魂(ψυχὴ 、プシュケー)そしてからだ(ϛῶμα、ソーマ)があることを語っています。
「平和の神ご自身が、あなたがたを完全に聖書なるものとしてくださいますように。あなたがたの霊(プネウマ)、たましい(プシュケー)、からだ(ソーマ)のすべてが、私たちの主イエス・キリストの来臨(パルーシア)の時に、責められるところのないものとして保たれていますように。」(Ⅰテサロニケ5:23)
「新約聖書ギリシャ語小辞典」では、霊(プネウマ)と魂(プシュケー)との違いについては以下のようにしめされています。
「プネウマは、神にかたどって造られた人間だけに与えられていて、神と「あなたと私」の関係で人格的な交わりを持つことができる能力、神の前に罪を悲しむ能力、神の愛や罪の赦しを受けて喜ぶ能力、人を真に人として生かす神からの生命力(神の霊)を受け止める能力であって、単に思考し、判断し、情緒を表現するプシュケーとは別個に、その奥深く秘められた能力また主体である。」
一言でいえば、霊は神と交わる能力、魂は人間の知・情・意の部分で、からだは、身体、肉体を示しています。
またマタイの福音書では、ソーマ(からだ)がプシュケーと対立して用いられています。例えば、イエスは、「からだ(ソーマ)を殺しても、たましい(プシュケー)を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろたましいもからだもゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。」(マタイの福音書10:28)とあります。クリスチャンを迫害する支配者は、からだを殺すことができますが、たましいを殺すことはできません。両方を殺すことができるのは、神ご自身です。ですから、支配者ではなく、神を恐れないと聖書は語っています。
第二のソーマも用い方の特徴は、現在私たちがもっているからだだけではなく、将来よみがえりの霊的からだについても語っていることです。イエス・キリストの復活は将来クリスチャンが復活することの初穂です。第一コリント書15章において、「天上の身体」と「地上のからだ」、「血肉のからだ」と「御霊に属するからだ」が対比され、キリストの再臨の時に与えられるクリスチャンの栄光のからだについて以下のように記されています。
「死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので撒かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので蒔かれ、栄光あるものによみがえらされ、力あるものによみがえらされ、血肉のからだ(ソーマ)で蒔かれ、御霊に属するからだ(ソーマ)によみがえらされるのです。血肉のからだ(ソーマ)もあるのですから、御霊のからだ(ソーマ)もあるのです。」(1コリント15:42~44)英語では「血肉のからだ」はnatural body.「御霊のからだ」はspiritual bodyと訳されています。パウロは、この栄光のからだが与えられることを心から待ち望んでいたのです。つまり主の再臨の時に、クリスチャンにはイエス・キリストと同じ御霊のからだ、栄光のからだ、朽ちないからだが与えられるのです。
「キリストは、万物をご自分に従わせることのできる御力によって、私たちの卑しいからだ(ソーマ)を、ご自分の栄光に輝くからだ(ソーマ)と同じ姿に変えてくださいます。」(ピりピ3;21)
第三のゾーマも用い方は、からだが教 会(ἐκκλησία、エクレーシア)に対して比喩的に用いられていることです。そこではからだの一体性と多様性が示されています。私たちのからだは、脳の指令によって動きますが、同時に様々な器官が働くことによって調和を以て保たれています。同時に教会(エクレシア)も、教会の頭なるキリストを中心に、聖霊の働きによって一つとされ、様々な賜物を与えられた信者によって構成されています。
「ちょうど、からだ(ソーマ)が一つでも、多くの部分があり、からだ(ソーマ)の部分が多くても、一つのからだがあるように、キリストもそれと同様です。—-あなたがたはキリストのからだ(ソーマ)であって、ひとりひとりはその部分です。」(第一コリ12:12,27)
教会の頭がキリストであり、信者がその器官、部分であることは、教会がキリストを中心とした有機体であることを示しています。
「キリストによって、からだ全体は、あらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに建てられることになります。」(エペソ4:16)