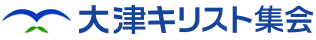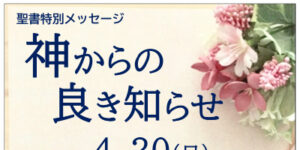第26回 「聖書入門ーキーワードで読む」
第二十六回 聖霊(holy spirit, Άγιο Πνεύμα 、 ‘ο Παρακλητος、 )
「聖霊についてのギリシャ語の言葉」
新約聖書では、聖霊を示すものとして「御霊」(プネウマ(πνεύμα)、「聖霊」(プネウマ・ハギオン、πνεύμα άγίον)そして「助け主(パラクレートス、παράκλητος)です。「御霊」は、霊に定冠詞をつけて神の霊を表示します。つまり τό πνεύμα、英語ではthe spiritです。霊「プネウマ」自体は、人間の霊もあるので、定冠詞をつけて区別する必要があります。
「新約聖書ギリシャ語辞典」では、「原則として御霊が一個のPerson として、またはDivine Person として言及される時には冠詞をつけ、御霊の作用や影響力や賜物に言及する時には、冠詞をつけない。」と説明されています。それに対して、霊に聖なるという形容詞がつくと「聖霊」と訳されています。基本的に「御霊」と「聖霊」は同一です。また聖霊が「助け主(パラクレートス)として表示されている箇所も存在します。イエスは、「私はあなたがあのために助け主を遣わします。」(ヨハネ16:7)と語られ、続けて「真理の御霊」ないし「御霊」と言い換えています。(ヨハネ16:13,14)なおこの言葉は、新約聖書で、ヨハネの福音書14:16、26、15:26、16:7〜8、1ヨハネの手紙2:11と5回だけ用いられています。「助け主」のギリシャ語パラクレートスのパラは、脇に、またかたわれらにを意味し、クレートスは、呼び出された者を意味します。弁護人、執り成す者、慰め主という意味です。つまり聖霊は、クリスチャンを助け、執り成し、慰め、助けたりする存在です。パラクレートスの動詞は、パラカレオ―(παρακαλω)で側に呼び出すという意味です。
「聖霊は、三位一体の神」
聖霊は、私たちの「助け主」とありますが、この言葉は正しく理解する必要があります。つまり創世記にあるようにエバがアダムの「助け手」(helper)(創世記2;20)であると同じ意味で「助け手」ではなく、「助け主」、つまり三位一体の神です。聖霊は、「永遠」、「全知」、「全能」、「聖さ」、「愛」といった神の属性をすべて持っておられます。聖霊は、三位一体の神の第三位格です。聖書には、「あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け」(マタイ28;19)とありますし、また「主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなたがたすべてとともにありますように」(Ⅱコリント13:13)と三つのものが一体のものとして記されています。なお「三位一体」(trinity)という言葉自体は聖書にはありません。
「聖霊は人格」
聖霊は単なる超自然的な力や影響力ではなく、人格です。人間は、物や自然的法則などとは交わりを持つことはできませんが、聖霊が人格であることより、交わりをもつことができます。それでは人格とは何でしょうか、人格には知・情・意志の特徴があり、理性的な認識を持ち、感情を持ち、また意志を持って行動する主体です。聖書には、「御霊は、すべてのことを、神の深みさえも探られる方です。(Ⅰコリント2:10)とありますし、人間の心の中をすべて知っておられる方です。また聖霊には感情があるので、パウロは無慈悲、憤り、怒り、ののしりをする人に対して、「神の聖霊を悲しませてはいけません」(エペソ4:30)と警告しています。。また聖霊は意志をもって人間を導かれる方ですので、「御霊は弱い私たちを 助けて下さいます。」(ローマ8:26)と記されてあります。また聖霊は、「耳のある者は、御霊が諸教会に告げることを聞きなさい」(黙示録2:7)とあるように、私たちに語られ、交わりを持ちたいと願っておられます。以上、私たちは、聖霊が私たちにとっていかに身近な存在であるかを知ることができます。
それでは、具体的に聖霊の働きについて、信じる以前、信じた時、信じた後の信仰生活の三つにわけて考えていきます。
「聖霊の働き」
A 信じる以前
(1) 聖霊は、わたしたち人間に罪や裁きの現実を知らせます。聖霊の働きがなければ、人は自分の罪を自覚することはありません。イエスは。「その方【助け主】が来ると、罪について、義について、さばきについて、世の誤りを認めさせます」(ヨハネ16;8)と語られました。罪や裁きを示されて、人は悔い改めに導かれます。
(2) 聖霊は、イエス・キリストの十字架の贖いの価値をさし示します。
B イエス・キリストを信じた時に
(1) 聖霊はイエスを信じた人に「新しい生まれ変わり」(新生)をもたらします。イエスはニコデモに「人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。」(ヨハネ3:5)と語られました。
(2) イエスを救い主として受け入れた信者は、聖霊の証印を押され、聖霊が内住します。エペソ書には、「このキリストにあって、あなたがたもまた、真理のことば、あなたがたの救いの福音を信じて、それを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印を押されました。」(エペソ1:13)と記されています。またローマ人への手紙においては、「しかし、もし神の御霊があなたがたのうちに住んでおられるなら、あなたがたは肉のうちにではなく、御霊の内にいるのです。キリストの御霊を持っていない人があれば、その人はキリストのものではありません。」(ローマ書8:9)と記されています。聖霊の証印が押されていることは、、神の子供であることの証拠です。
(3) 聖霊は信者が、神の子であることを証します。ローマ書では、「聖霊御自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証しして下さいます。」(ローマ書8:16)と記されています。
C. クリスチャンの信仰生活や教会の歩みについて
(1) 聖霊は、神の愛を感じるように信者を導きます。
“この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。”(ローマ書5:5)神の愛を日々深く知ることによって、クリスチャンは信仰的に成熟し、キリストと一つに結びつけられていきます。
(2)聖霊は霊的真理を明らかにし、神の言葉を理解する力を与えます。
(3)聖霊は、信者を日々新しくします。 “私たちはみな、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿に変えられていきます。これはまさに、御霊の働きによるのです。” (Ⅱコリント3:18)高齢化社会において、パウロのように「たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。」(Ⅱコリンtト4:16)と言える人は御霊によって生きている人々です。
(4)聖霊は、クリスチャンの生活、教会の礼拝や奉仕において神の子を導きます。 “神の御霊に導かれる人はみな、神の子供です。((ローマ8:14)
(5)聖霊はクリスチャンが証をする力を与えます。 “私たちの福音は、ことばだけではなく、力と聖霊と強い確信を伴って、あなたがたの間に届いたのです。” (テサロニケ1:5)
(6) 聖霊はクリスチャンのとりなしをします。 “同じように御霊も弱い私たちを助けて下さいます。私たちは、何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身がことばにならない呻きをもって、とりなしてくださるのです。”(ローマ8;26)
Ⅲ 聖霊について気をつけること
(1) 聖霊は、「助け主」であるが神です。ですから、エバがアダムの助け主として造られたと同じ意味において、聖霊は助け手ではありません。私たちが神である聖霊の導きに従うべきであって、聖霊が人間に従うのではありません。聖書は御霊によって歩むこと、導かれること、前進することを命じています。
(2) 「御霊は私の栄光を現わされます」(ヨハネ16:14)と語られたイエスのことばに、聖霊とイエスの関係が明らかにされています。。この関係が見失われると、イエスより聖霊が重んじられることとなります。(ローマ8;26)また礼拝の対象は、神とイエス・キリストであり、聖霊ではありません。したがって、礼拝の対象としてクリスチャンは神様、イエス様と言いますが、聖霊様とはいわないのです。
(3) 同時に聖霊の働きはみことばと矛盾したり、それから逸脱するものではありません。みことばと矛盾するような聖霊の働きは、聖霊の導きとはいえないものです。
(4) クリスチャンにとって聖霊はすでに内住しているので、もっと信仰的に元気になるために、外からから聖霊を再度受けることを追い求める必要はありません。聖霊は、内側から働かれるのです。異言を語ることや癒されことを聖霊を受けていることの証拠とすることは間違 いで、信仰生活を破壊します。そのような考えに基づいていたずらに異言やいやしを追い求めれば、個人 の健全な信仰生活も教会の秩序も脅かされることになります。聖書が完成している今日、異言は廃れたと考える方が健全です。