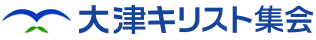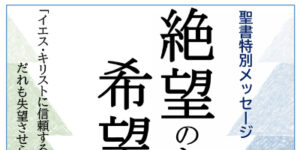聖書メッセージ86
石井十次(1865〜1914) -信仰と孤児のために生きた生涯
「プロフィール」
石井十次は1865年4月11日、宮沢県高鍋町に日向高鍋藩の下級士族の長男として生まれました。父の万吉は、1877年の西南戦争に西郷隆盛の側に立って戦った人物です。石井は宮崎で、医師萩原百々平を通して信仰に導かれます。そして彼は、医学の道を志し、岡山県医学校で学んでいた時、新島襄の教え子で、岡山基督教会の創始者であって金森通倫(1857〜1945)と出会い、1884年金森から洗礼を受けます。当時岡山の地はキリスト教伝道の中心地でした。石井は1912年の手記において、「自分が神を信じた幸福を感じると同時に、世の中にはいまだ天地の主なる神様を知らずに精神的孤児の生活をして苦しんでおられる同胞が沢山あることを思い、実に気の毒に耐えられないのであります。」と書き記しています。
「孤児院の開始」
日本で孤児院を始めて開設したことで知られるのが石井十次です。彼はまた日本では、「日本の児童福祉の父」として知られています。彼の生涯は、2018年に上映された「石井のお父さんありがとうー岡山孤児院・石井十次の生涯」で映画化され、松平健が主演を務めました。映画のポスターには、「親のない孤児よりももっと不幸なのは心の迷い子、精神の孤児なのです。」という石井の言葉が紹介されています。
石井は、上阿知の大師堂で孤児院を始めて後、岡山市の門田屋敷にある臨済宗三友寺の一画を借り受け、1887年9月、3人の男児をうけいれて、「孤児教育会」(岡山孤児院の前身)を始めました。対象年齢は6〜12歳です。その後孤児の数は膨れ上がり、1890年に100名に達しました。石井の妻品子が孤児の養育の中心的存在でした。彼は、1889年、医学の道を捨てて、孤児救済事業に専念するようになります。彼の1日は二時間の祈りを持って始まり、神の声を聞くことを日課としていました。彼の孤児院での働きは、孤児たちへの愛と聖書の福音を伝えたいと言う熱心に支えられていました。彼は孤児院において祈祷会を開いたり、聖書講義をして、キリストの福音を伝えました。
石井は、当初は会員組織を作り、寄付金を徴収していましたが、イギリスの孤児院経営者ジョージ・ミラー(1805〜1898)の影響を受けて、会員募集を中止し、臨時給付金だけにしました。この頃の彼の日記を紹介します。1889年4月18日の日記には、「人に頼らず、ただ神様に依頼し、神様の証人となり、神様に栄を帰すべきことを決心せり」と書き、欄外に「独立は神様と共にあるを言う。孤立と誤るべからず。」と書き込んでいます。人間に依存せず、ただ神の御手に信頼しての決断でした。人間的に寄付する人を増やすのではなく、神が人を動かして与えてくださることを優先したのです。しかしその結果、孤児院は財政緊迫状態に陥り、米麦が不足する状態に陥りまし。しかし、その度に神のくすしい導きによって、不足が満たされ、石井は神は生きておられるという確信をもつに至ったのです。石井は孤児院をクリスチャンホームとみなし、そこにおいて愛が溢れるきずなが築かれるように切に祈りました。石井と妻品子が孤児院の父母の役割を果たしました。岡山孤児院の財政的支援のために重荷を持ち、動いていたのがアメリカンボードの宣教師ペティ、そして救世軍の山室軍平、そしてとりわけ倉敷紡績会社の大原孫三郎たちでした。
「美濃大地震」
岡山孤児院のターニングポイントは、1891年10月に愛知・岐阜地方を襲った濃尾大地震でした。この地震で6000人以上の死者が発生したと言われています。石井は震災孤児を百人ほど岡山孤児院に引き取りましたが、その結果、1994年1月には孤児の数は263人に増加していました。また彼は、孤児の教育の必要性を痛感し、1897年12月に岡山孤児院尋常高等小学校を開校しました。また財政的な必要や孤児たちが開墾によって生計を立てることを目的とし、故郷の宮崎県高鍋町に近い山谷の台地、茶臼山の開墾のため、1894年年長の孤児が52名、職員が4名派遣され、開墾が始められました。
岡山孤児院の最大の危機は、1895年、コレラが大流行し、孤児院を襲ったことでした。この出来事は、石井に大きな試練をもたらしました。石井は大病を患い、妻の品子は30歳で死去し、4人の孤児がなくなっています。しかしこの時に、石井は信仰の大転換を経験します。石井の信仰は今までキリストの愛を実践することに主眼が置かれていました。しかし、妻の死や自らの大病を経験し、イエスの十字架の救いに目が開かれるようになります。彼の日記を、文章をわかりやすくして紹介します。
「イエス・キリストは、神の子にして、私たち人類のために血を流されたこと明白なるや、不思議にも感謝の涙と共に心情温かとなり、喜び満ち溢れる。」
そして彼は、1895年10月22日に岡山基督教会にて信仰告白を行なっています。第一に、「イエス・キリストは神の独子として、人類のために贖罪の血を流したまいしこと」、第二に、「聖書は神の言葉にして、我らが信ずべき経典たること」、第三に、信仰の旗色を鮮明にし、福音宣教に邁進することです。
「東北地方の大凶作」
1905年、大凶作が東北地方を襲い、飢饉が生じたので、石井は1906年総勢824人の孤児を岡山孤児院に収容しました。在院児と合わせると1200人を超える大集団となります。1907年4月の時点で、岡山孤児院は、敷地面積3、7ヘクタール、建物の数は78棟、孤児の数は1000人前後、職員110余名の規模に達していました。収容児の数が減っているのは、このころ里子に出す委託制度を導入したからです。この里親制度は、孤児を10歳まで預け、それが終わったら孤児院に引き取って職業教育をするもので、養子縁組制度とは異なっていました。これだけ孤児の数が膨れ上がると、孤児院を維持することに力を注がざるを得なくなります。
1906年石井は、今度は腸チフスに襲われます。彼は病魔と苦闘している時、幻をみました。キリストが大きなカゴを背に現れ、数百人の児童が入れられていましたが、外に残っている三百人の子供を次々とかぎに押し込んで、全部入れてしまうとキリストは、「もう済んだのか」と行って立ち上がり、十次もかぎに手を掛けて手伝って運んだのです。その幻の真意を、石井は以下のように述べています。
「自分は大勢の子が次々と来てどうなるか心配しているけれど、「孤児院を背負っているのはお前ではなくキリストだ。お前は孤児院が狭くてもう子供を入れることができないと思っているが、今見たとおりいくらでもはいる。お前は心配せずにありたけの力を出して、かぎの底に手を掛けて手伝いさえすればよい。」
1908年11 月、石井は、岡山孤児院の収容が限界に達したこともあり、将来の孤児たちの生活を念頭において、岡山孤児院茶臼原農林部を岡山孤児院支部茶臼原孤児院と改称し、本格的に茶臼原(ちゃうすばる)で開墾事業を行い、本格的に孤児救済活動を展開します。
「茶臼原への移転」
茶臼原の施設が独立した孤児院として認められた後、岡山からの移住が始まりました。また石井は1910年3月、岡山孤児院の男子部を茶臼原に移転する決定をしました。これにより、男子部全員107人と女子部64人、主婦7人の総勢178人が岡山を離れ、1911年3月に全面移転が完了したのです。石井は、茶臼原に「真正の天国を建設すること」を理想とします。
石井は1913年茶臼原の働きのための憲法を制定しました。その第1か条は
「天は父なり、人は同胞なれば互いに相信すべきこと。」というものでした。
「金森通倫の手紙」
以前、岡山教会の牧師で石井にバプテスマを施した金森通倫は、石井の病が深刻なことを心配し、茶臼原における石井の働きすぎや悪戦苦闘の生活を心配したのか、または石井の信仰を心配したのか、1913年11月6日に、以下のように書き送っています。それは、石井自身が1895年に経験した聖書の最も重要な真理の再確認でした。金森自身は、一時は正統な信仰から外れていましたが、妻の死という苦しみを通し、この聖書の真理に目が開かれていました。彼の石井への手紙は、信仰の基本に立ち返ることの重要性を訴えたものです。
「石井君よ。僕はもうすべての世の中の議論や理屈を捨てて、単純な最初の信仰に立ち返りました。神は愛の天父であること、キリストは私のために十字架に死し給うたこと、私は罪人の中の大罪人であること、以上の単純なるキリスト教の根本真理を僕は今更の如くに信ずるようになった。——君もどうぞ最初の単純な信仰を持ちたまえ。我々を救うものは、キリストの十字架のほかなし、議論はいらぬ。理屈はいらぬ。信ずべきはキリストの十字架、頼るべきはキリストの十字架、望むべきは天国の福である。——お互いに最初の単純なる信仰にかえり、神を愛し、キリストを愛し、天国を望んで進み来るものである。この手紙は、君の上に神の祝福あらんことを。」
石井は茶臼原孤児院で1914年一月天国を望みつつ、神に召されます。享年48歳です。孤児のために全生涯を捧げた信仰の生涯でした。
「石井十次死後」
石井の死後、彼の後継者になったのは石井の孤児院の働きを財政的に支えてきた倉敷紡績会社社長である大原孫次郎(1880〜1943)でした。彼は、岡山の孤児院を解散し、宮崎の茶臼原での孤児院や開墾事業も停止しました。それは大原が、岡山や茶臼原での孤児院の事業が採算に合わないこともありましたが、石井の死後、石井の精神が失なわれ、組織や事業が一人歩きしていると判断したからです。ただ大原は、1917年大阪に石井記念愛染園を設立し、石井の精神を汲んだ福祉活動を展開しています。また戦後1947年には、茶臼原の地に石井記念友愛会が認可され、児童養護施設を初め、多彩な福祉活動が展開され、石井の精神と事業が継続されていきます。
石井の孤児福祉事業の歴史的評価は様々です。たしかに、そこには失敗や挫折もありましたが、まだ国によって孤児に対する支援が行なわれていなかった頃、石井が、率先してキリストの愛に促されて、困窮する孤児を多数受け入れ、聖書に基づいて、教育し、将来の人材を育成しようとしたことは、歴史に深く刻まれており、その精神は後世に受け継がれています。
参考文献
横田賢一 『岡山孤児院物語』(山陽新聞社、2002年)
柴田善守「石井十次の生涯と思想」(春秋社、1978年)
城山三郎『わしの眼は十年先が見える 大原孫三郎の生涯』(新潮文庫、1997年)