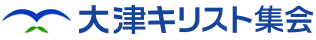聖書メッセージ 83|乗松雅休(のりまつまさやす、1863〜1921)ー朝鮮伝道に捧げた生涯
乗松雅休(のりまつまさやす、1863〜1921)
ー朝鮮伝道に捧げた生涯ー
「乗松のプロフィール」
乗松雅休は、1863 年松山藩士乗松忠次郎の長男として現在の松山市で生まれます。彼は1887年に24歳で洗礼を受ますが、1888年にプリマス・ブレザレンの独立伝道者ハーバード・ブラント(1865〜1942)の影響を受けて、プリマス・ブレザレン(同信会)の伝道者となります。プリマス・ブレザレンで有名な人は、創始者のJ ・N・ダービー(1800〜1882)や孤児院の創設で有名なジョージ・ミュラー(1805〜1898)です。
プリマス・ブレザレンの特徴は、第一に聖書を誤りのない霊感された神のことばとして信じ、受け入れたこと、第ニに牧師制度を否定し、お互いに兄弟姉妹(ブレザレン)と呼ぶ教会形成を目指したこと、そこには聖職者と平信徒の違いはなく、牧師や先生と呼ばれることもありませんでした。第三に、毎週礼拝の時に聖餐式(パン裂き集会)を行い、パンとぶどう酒に与り、イエスの十字架の犠牲を記念したこと、第四に、キリストの再臨を熱心に待ち望んだこと、第五に日本国内外の伝道に熱心であったことです。
乗松は、最初、国内伝道者として働いた後、日清戦争後の1896 年に朝鮮伝道を志し、日本プロテスタント史上、最初の海外伝道者となります。彼は、最初京城(現在のソウル)で伝道した後、1900年8月にソウルの南郊外にある水原(スウォン)に移り、一時病気療養のため5ヶ月ほど帰国した期間を除き、1914年に帰国するまで、約14年間を水原で福音を宣べ伝えます。
「水原での伝道」
彼の宣教の特徴は、現地の人々と同じ生活をするということでした。朝鮮の服を着て、朝鮮の言葉で話し、住宅も食器も朝鮮式で、子供には朝鮮の言葉だけを教え、日本語は教えなかったそうです。また子供が四人いたにもかかわらず、極貧の生活中で伝道していました。彼は朝鮮の人と衣食住を共にし、朝鮮人になり切ろうとしました。そうした彼の姿勢から徐々に、現地の人々との心の扉が開かれ、乗松の福音宣教が実を結んで行きます。彼の伝道のことばは、簡単明瞭であり、「ハナニム(神様)は愛であって、罪の下に打ちひしがれている人類を救おうと独り子イエスをわれらにお送りくださった」というものでした。彼は市場でバイブルを片手に、天を仰いで祈り、「活けるキリスト」を伝えたり、戸別訪問をして静かに福音を説き、聞いている人に大きな感動を与えました。そこにはイエスが生きて働いている臨在感がありました。こうして乗松の働きが知られるようになり、水原の人々は乗松を尊敬するようになり、乗松の伝道によって約一千人の人がイエスに対する信仰を持ったといわれています。
「乗松の悲哀」
彼の朝鮮伝道における一番の試練は、1908年に乗松の最愛の妻で、彼の伝道を献身的に支え、三人の子供を育ててきた乗松常子が33歳で肺炎で召天したことでした。乗松は深い悲しみに沈み、「悲哀の人」であるイエス・キリストを慕い求めます。彼はその心境を、次のように述べています。
「私は、昨年以来しばしば『涙の谷』を過ぎ行くように導かれ、我が目に絶えず涙を流しています。自分のことをかえりみては、ただ大能の御手の下に自らを卑くして主の憐れみをこうのみです。我が霊をして切に『悲哀の人』である御方を思い慕います。涙をもってこのことを主に感謝せざるを得ません。」
彼は、神の慰めにより、この悲しみから立ち上がり、福音を宣べ伝え続け、1914年に帰国して、1921年に肺炎で小田原で召天しています。同じプリマス・ブレザレンの信者で、白洋舎の創業者である五十嵐健治が「骨は必ず朝鮮に埋めてくれ」という乗松の遺言に基づき、水原に遺骨を運んでいます。ちなみに五十嵐健二は、彼の生涯を描いた三浦綾子著『夕あり、朝あり』で知られるようになります。
「日韓保護条約、韓国併合、三・一独立運動」
朝鮮伝道は、日本の朝鮮支配に対する反発の故に障害の多いものでした。日本人であるというだけで嫌われるという逆風が吹いていました。
1905年に保護条約(第二次日韓協約)が締結され、韓国政府は日本によって安全保障と外交の権限を奪われます。1909年にはハルビンで当時の韓国統監府の統監であった伊藤博文が安重根によって暗殺された事件が起きます。この事件が象徴しているように、抗日運動はエスカレートしていきます。1910年には韓国併合が行われ、総督府による武断政治によって日本の植民地支配と朝鮮民衆に対する弾圧が強化されます。乗松が日本に帰国した後に起こった1919年には、朝鮮全土で三・一独立運動が発生し、水原では、独立運動の指導者とみなされた23名が日本軍や警察によって殺害され、暴動の温床とみなされた提岩里教会が焼き払われるという残虐な事件が起きています、これ以降水原は、日本に対する憎しみと怨念を象徴する代名詞となります。そうした中でも水原の人々の、乗松に対する尊敬と信頼は変わらず、乗松は今でも「暗闇の中に輝く光」として輝き続けています。
「乗松についての証言」
乗松によってイエス・キリストを信じ伝道者となったキム・テヒは、1921年2月14日の乗松の葬儀で、「 イエス・キリストは神様であるのに、人とおなりになった。この愛に励まされて、乗松兄は朝鮮の人を愛しました。世の中に英国人になりたい人は沢山あります。米国人になりたい人も沢山あります。けれども乗松兄は朝鮮の人になりました。この愛はいかなる愛でありましょうか。」
また同心会の詩人である李烈(イヨル)は、1979年に同心会の水原教会堂が建設された時、その献堂式で乗松について次のように述べています。
「私たちは、豊臣秀吉の日本を憎みます。伊藤博文の日本を憎みます。彼らは武力でわが国を踏みにじり、手練手管で我が民を籠絡(ろうらく)しました。しかし、かの名もなき乗松の日本を愛します。乗松のような善良な日本人を愛します。彼は、暗闇に閉じ込められた我が国に、真の光を証しするために参りました。絶望の底で、ため息をつく我が民に、いのちのみくにを望み見させました。彼は、韓国服を着、韓国語を語り、麦藁の家で、我が民の中でも一番貧しい人のように暮らし、我が国を自分の国よりも、自分のこどもよりも、もっと愛しました。」
1922年乗松は、水原で埋葬され、墓碑が設けられますが、そこには「生きるも主のため、死ぬるも主のため、始め人のため、終わりも人のため、その生涯まごころをつくして愛し、おのれ主の使命を帯びて、その一切の所有を捨てて、夫婦同心、福音を朝鮮に伝う。」と刻まれています。
参考文献
大野昭 「最初の海外伝道者、乗松雅休覚書」(キリスト新聞社、2000)
飯沼二郎『日本帝国主義下の朝鮮伝道』(日本基督教団団出版局、1985)
中村敏『日韓の架け橋となったキリスト者 乗松雅休から澤正彦まで』(いのちのことば社、2015)