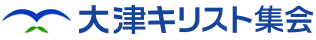聖書メッセージ47|ドストエフスキーと聖書(2)
ドストエフスキーと聖書(2)
―『罪と罰』―神が存在しなければすべてが許されるー

ドストエフスキー(1821-1881)は、世界的な文豪で日本でも彼の小説はよく読まれています。その中でも、『罪と罰』(1865)、『白痴』(1867)、『悪霊』(1870)、『カラマーゾフの兄弟』(1879)は、特に親しまれている小説です。聖書メッセージ20では、「ドストエフスキーと聖書」で『カラマーゾフの兄弟』の一こまを紹介しました。今回は、『罪と罰』を通して、ドストエフスキーと聖書のかかわりを考えます。
彼は、1849年、反政府活動の嫌疑で逮捕され、処刑を宣告されますが、まさに死刑が執行される直前に、皇帝から恩赦を与えられ、命拾いした経験があります。彼はこの経験を通して、神の存在と生きる目的を真剣に考えるようになります。ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』でイワンが語った言葉に、「神が存在しなければ、すべてが許される」という言葉があります。この言葉に、『罪と罰』の主題が表現されています。『罪と罰』の中でよく使われている言葉が「踏み越える」という言葉です。それは、法律を「踏み越える」だけではなく、神の定めた善悪の規範を「踏み越える」ものであり、さらには、罪責感を生じさせる「良心」をも「踏み越える」ものでした。最終的な審判者である神がいなければ、すべてが許され、一切の限界が踏み越えられ、他者のみならず自己の人間性を破壊してしまうのです。それが、『罪と罰』の主題です。
「ラスコーリニコフの殺害」
この神の権威に真っ向から挑戦したのが、無神論者ラスコーリニコフです。彼は、ぺテルスブルク大学を中途退学せざるをえないほど貧しかったのですが、優れた頭脳を持つ学生でした。彼は自分の置かれた社会的な境遇に怒りをもっていました。彼は、自分も借金をしているなじみの金貸しの老婆を殺害することを思い立ち、決行します。それだけではなく、偶然に老婆の家に来て、犯行を目撃したリザベータをも殺害します。彼にとって老女は、「しらみ」のような存在で、生きる価値のない、死んでしまった方が社会にとって益となるような存在でした。彼は、自分の行動を正当化する思想を思い立ちます。つまり、英雄、非凡な者は、自分で善悪を定め、何をしても許されるという考えです。ラスコーリニコフが念頭に置いていたのは、ナポレオンでした。彼は、ナポレオンを想定して、「ああいった人間たちは、もとからして違うんだ。すべてを許された本当の支配者は、—–パリで大虐殺をやらかしたり、エジプトに軍隊を置き忘れたり、モスクワ遠征に出て五十万もの人間をむだづかいにしたり、——やることがちかうんだ。それで死んだら、銅像が建てられる。要するに、すべてが許されているんだ。」と言っています。
これは、ニ―チェの「超人思想」につながる危険な思想で、英雄―大衆、非凡人―凡人、上級国民―一般国民という差別的構造を人間に設け、自分は上級国民、エリートであるので、法律を破って何をしてもいいという意識です。こうした考えは、人種的に優秀なアーリア人は、世界やドイツをがん細胞のように浸食し、腐敗させ、死滅させるユダヤ人を抹殺してもかまわないというヒトラーの反ユダヤ主義にも流れ込んでいきます。。
「ソーニヤとの出会い」
しかし殺人を犯してからのラスコーリニコフは、自分が殺人を犯したことに、恐怖、不安、精神の不安定を覚え、彼の英雄としての自己認識は、崩れていき、赤裸々な弱い自己の姿をさらけ出し、病気で寝付くようになります。しかし、精神的に追い詰められている時に、彼は、ソーニヤとの出会いを経験します。ソーニヤは娼婦(しょうふ)で、「自分がけがれた、罪の女」であることを自覚していました。しかしソーニヤの生き方は、ラスコーニコフの利己主義的、自己閉鎖的で、他人を道具と考えるような生き方とは正反対でした。ソーニヤは、酒飲みで一家を貧困に追いやっている父マルメラードフや、傲慢で虚栄心が強く、肺を病んでいて、3人の幼児をかかえている義母カチェリーナをも愛し、一家のために、娼婦となり、家計を支えています。そこにあるのは、マルメラードフやカチェリーナが辿ってきた人生の苦難に対する共感能力と思いやりでした。人の心の深みや痛みを理解し、他者の存在をありのまま受け入れる心の態度です。人間的に見るならば、マルメラードフは、老婆と同様に、あるいはそれ以上に生きる価値がない存在ですが、ソーニヤにとっては大事な存在です。
ラスコーリニコフは、ソーニヤとの第一回目の会話(第四部第四章)において、ラスコーリニコフは「君だって同じことをしたんだ。君もやっぱり踏み越えたんだ。君は自分で自分に手を下した。いのちを滅ぼした」と言い、共に呪われているものとして、一緒に人生を歩もうと迫ります。こう言いつつも、彼は、ソーニヤの中に自分とは全く異なるものを見、彼女の深い愛に、自分の心を開くようになります。この時にマリアは、ラスコーリニコフに、ヨハネの福音書の11章1-27節までのラザロの復活の記事を読んであげています。それは、一度死んだラザロがイエス・キリストによってよみがえらされ、それを見ていた人々がイエスを信じたという箇所です。
ラスコーリニコフは、ソーニヤとの第二番目の会話(第五部第四章)で、今まで誰に対しても隠していた犯罪の事実とその動機を告白します。それに対してソーニヤは、「あなたは、神様から離れたのです。——ああ神さま!この人には何もわからないのです。」と述べ、ソーニヤは罪を告白し、苦しみを受けて罪を償(つぐな)うために自首することを勧めます。しかしこの時に至っても、ラスコーリニコフには罪責観はありませんでした。彼はソーニヤに対して、「単にしらみをつぶしたのではないか、ソーニヤ、何の役にもたたない、けがらわしくて、有害なしらみをさ。」と述べるのです。それに対するソー二ヤの言葉です。
「だまって!からかうのはやめて、ああ神様を冒とくするのはやめて。何も、何もわかっていらっしゃらない、あなたはああ、神様!何も、何も、この人はわかろうとしない!」
そしてソーニヤは、ラスコーリニコフに十字路に行って、「私は人殺しです」と告白し、懲役の苦しみで、罪を償うことを勧めるのです。ラスコーリニコフは、ソーニヤの勧めにしたがって最終的に自首し、裁判で有罪になり、シベリア送りになりますが、彼に自分の犯した罪に対する悔い改めがあったわけではありません。ソーニヤは、シベリアまでラスコーニコフと一緒についていきます。そして病気の時以外は定期的に刑務所を訪問し、彼を支え、また仲間の囚人からも愛される存在となります。
「ラスコーリニコフの変化」
このソーニヤとの出会いを通して、ラスコーリニコフは変わったのでしょうか?当初彼は、自首して、シベリア送りになっても、自分の罪を自覚し、赦しを求めようとしませんでした。彼が変わる一つの転機は、彼がシベリアの病院で見た悪夢でした。夢はドストエフスキーの小説では、いつも重大な意味を持っています。この悪夢は、アジアの奥地からヨーロッパにひろがって、多くの人を死に至らしめている疫病の夢でした。この疫病に感染すると、「それに感染した者たちは、病気にかかる前には考えられもしなかった強烈な自身をもって、自分はきわめて賢く、自分に信念は絶対に正しいと思い込み」、そこから、対立、戦争、飢饉が発生し、人類が滅びていくという悪夢なのです。実にこの感染症こそ、自分は英雄で、非凡な存在で、なにをしても許されるという、ラスコーリニコフが当初抱いていた思想であったのです。この悪夢を通して、自分がナポレオンの超人思想に感染し、それがいかに恐ろしいことであるかを彼は理解しました。
シベリアでの生活を通して、彼は徐々に変えられていきます。「エピローグ」で彼はラスコーリコフのシベリアでの服役生活を描いています。ラスコーリニコフを変えたのは、ソーニヤの無私の愛でした。
「彼はよみがった。そして、それが彼には、わかっていた。生まれ変わった存在のすべてで、いっぱいにそれを感じ取っていた。」と記されています。彼は、自分から聖書の福音書を開いて、読みます。それは、最初にソーニヤがラスコーリニコフに読んであげたヨハネの福音書11章の死んだラザロの復活のところでした。『罪と罰』の終わりにラスコーリニコフは、「彼女の信じることが、今このおれの信じることじゃないなんてことがありうるのか?」とまで述べています。ソーニヤの愛を通して、彼はソーニヤと同じ信仰に導かれていきます。ラザロの復活は、イエスが一度死んだラザロをよみがえらせる記事です。ドストエフスキーにとって復活は、自己中心的で神にも他者にも自己を閉ざしている人間が、一度死んで、罪赦されて、新しい魂に新生することでした。ドストエフスキーは、『罪と罰』の最後で、期待を込めて、ラスコーリニコフについて、次のように語っています。
「しかしここには、もう、新しい物語が始まっている。一人の人間が、一歩一歩更生していく物語が、段々と生まれ変わって、だんだんと一つの世界から別の世界へと移っていき、新しい、今までまったく知らなかった現実を知る物語が始まっている。」
森有正は、この所に触れて、「ラスコーリニコフは、自分の罪を、聖書を知り、イエス・キリストを知った日に、初めて自覚するであろう。『罪と罰』は、それへの希望を持って閉じる」と書いています。実にソーニヤは、ラスコリニコフの魂の復活を祈りつつ、最後まで彼に従い、苦しみを共にします。
「参考文献」
ドフトエフスキー『罪と罰』』(1~3巻)(亀山郁夫訳、光文社、2019年)
森有正『ドストエフスキーの覚書』(筑摩書房、1979年)