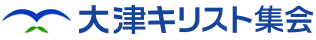聖書メッセージ28「太宰治と聖書-私は山に向かって目をあげる-」
第28回「太宰治と聖書-私は山に向かって目をあげる-」

太宰治(1909-1948)は、日本の近代文学者の中でも聖書を最も真剣に読んだ人であった。彼の短編小説は、聖書からの引用で満ちている。彼は、志賀直哉などを念頭に置いて、死の直前に発表した「如是我聞」という短編随筆の中で次のように述べている。
「君は、外国文学者のくせに、バイブルというものをまるでいい加減に読んでいるらしいのに、本当にひやりとした。古来、紅毛人[西洋人]の文学者で、バイブルに苦しめられなかった人は一人としてあったであろうか。バイブルを主軸として回転している数万の星ではなかったのか。」
たしかに太宰の小説家としての生涯は、酒乱、薬中毒、奔放な女性関係、三度にわたる心中事件、度を越した浪費という堕落した生活であった。しかし、彼は、そうした腐敗や暗黒の只中で、心の奥深くで、必死に神に助けを求めようともがいていた。結果として太宰は、救いを見出すことができず、1948年6月に愛人山崎富栄と共に玉川上水で心中事件を起こし、自分の短い生涯に終止符を打ったのである。享年39歳の若さであった。
太宰は、1930年の最初の心中事件で、自分は助かったものの、相手の女性は死んでしまったこともあり、深刻な罪意識を抱いていた。そして過去の出来事が走馬灯のようにフラッシュ・バックして、彼を苦しめた。彼は、死の一カ月前に書いた1948年の「人間失格」において、太宰の分身である主人公の大葉葉蔵に次のように言わせている。
「恥の多い人生を送ってきました。—–人間、失格。もはや自分は、完全に人間でなくなりました。」
これは太宰が酒に溺れ、モルヒネ中毒の地獄に落ちて、病院に入院した時を回想して書いたものである。
それでは、太宰にとって聖書とは何であり、彼は聖書をどのように読んだのであろうか。一言でいうと、彼は自分の人生は神の前に総決算をしなければならず、審判者である神の前に立たなければならないことを自覚していた。彼はドストエフスキーの『罪と罰』を読み、
罪には必ず罰、つまり神の審判があることを理解した。こうした緊張感は、彼の小説や日常の言動においても現わされていた。彼は、そのことを絶えず意識して生きてきたのである。
太宰は彼を慕っていた小山清が「神はありますか」と質問したのに対して、「あると思う。もし神がいなかったら、僕たちが人知れずした悪事は誰が見ているんだ」と答え、「神は帳面を持っていて、その神の帳面には、僕たちがやった人には計り知ることのできない悪事も善事もみな記録してあるんだ」とつけ加えている。
全知の神の前に立った時、消すことのできない客観的証拠があり、その証拠を突き付けられ、有罪判決を受けなければならないというのである。この神の帳面に書き込まれる罪は、太宰の心の帳面にも書き加えられ、太宰は苦しんだ。彼は、『人間失格』の中で、大葉を通して、次のように言わせている。
「自分は神にさえおびえていました。神の愛は信じられず、神の罰だけを信じているのでした。信仰、それはただ神のむちを受けるために、うなだれて審判の台に向かうことのような気がしているのでした。地獄は信じられても、天国の存在はどうしても信じられなかったのです。」
太宰は、聖書のイエス・キリストの言葉を真剣に受け止め、その基準に遠く離れている自分の姿を見出さずにはおられなかった。彼は、『如是我聞』において、「私の苦悩のほとんど全部は、あのイエスという人の『己を愛する如く、汝の隣人を愛せよ』という難題一つにかかっているといってもいいのである。」と告白している。太宰が人を愛しようと真剣に努力をしたとはいえないが、少なくとも彼は、自分が人を愛せないほど徹底して自己中心的で、醜いエゴイストであることを自覚していたのである。そして正義の鉄槌は必ず自分に下されることを信じていた。そうであるがゆえに彼の苦悩は深かった。道楽に逃避しても、彼の心は苛まされていた。
太宰がやはり晩年に書いた『斜陽』や『トカトントン』には、次の聖書の言葉が引用されている。「からだを殺しても、魂を殺せない人などを畏れてはなりません。そんなものより、魂もからだも、ともにゲヘナ[地獄]に滅ぼすことのできる方を畏れなさい」(マタイの福音書10章28節)
この点について文学評論家福田恒存は、「太宰治は、自己を責める神は発見したが、自己を赦す神は発見しなかったのである。」と述べている。重要な指摘である。
この点に太宰の聖書解釈、彼の神観の一面性があった。太宰は、死の直前に書いた『桜桃』の冒頭に旧約聖書の詩篇121篇1節の最初の一文、「われ、山にむかいて、目を挙ぐ。-詩篇、第百二十一。」が引用されている。この詩篇121篇の一節と二節、三節を新改訳聖書(第三版)から紹介してみよう。
「私は、山に向かって目を上げる。私の助けは、どこから来るのだろうか。私の助けは、天地を造られた主[神様]から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方は、まどろむこともない。」
太宰は、山に向かって目を上げ、神に助けを求めようとしたが、助けが創造者である神か
ら来ることを信じることができなかった。そのことのゆえに、彼は第二節の「私の助けは主
から来る」と続けることができなかったのではないだろうか。
太宰は神に助けをもとめようとしたが、できなかった。なぜなのか。彼は罪意識に苦しんだが、神からの罪の赦しを信じることができなかった。なぜなら、彼は、罪を裁く審判の神のみを信じて、罪を赦す愛の神を信じることができなかったからである。したがって、彼は、遺作『桜桃』を書いて、神から反転して、自殺に向かったのである。それが彼の結末であった。
太宰治の苦しみを理解しようとするなら、私たちは太宰を越えていかなければならない。太宰の心の奥深くにあった「神への渇き」が、真の救いに至ることを望まざるをえない。それは、山に向かって目を上げ、神の救いを待ち望むことである。それはまた、罪を裁く審判者である神のみならず、神の愛を知ることである。つまり、ひとり子イエス・キリストに私たちすべての罪を負わせ、私たちにではなく、全く罪のない神の子キリストに裁きを下された神の愛である。ひとり子さえも十字架につけるほどまでに私たちを愛された神の義と愛を知ることによって、人は救われるのである。キリストを救い主として信じ受け入れることによって、天国への門が開かれるのである。
「神はそのひとり子[イエス・キリスト]を世に遣わし、その方によって私たちに、いのちを得させて下さいました。ここに神の愛が示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました、ここに愛があるのです。」(Ⅰヨハネ4章9,10節)
皆様も、神を求めてみられませんか。大津集会では、毎日曜日に聖書を学んでいますので、
勇気をもってドアをノックしてください。大歓迎です。
参考文献 野原一夫 『太宰治と聖書』(新潮社、1899年)
長部日出雄 『桜桃とキリスト』(文春文庫、2005年)
文責 古賀敬太