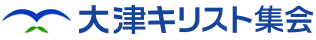第27回 良心(Conscience、συνειδησις,シュネイデーシス)
第27回 良心(Conscience、συνειδησις,シュネイデーシス)
「良心の定義」
シュネイデーシスは、新約聖書で30回使用され、特にパウロの書簡に20回使用されています。この言葉は、シュン(共に)とイデイン(知る、見る)を組み合わせたものなので、共に知る、共に見る者を意味します。英語で良心は、conscienceと言いますが、やはりcon(共に)+science(知る)の組み合わせです。共に自分の傍にあって、自分の思いや行動を自分と共に見つめ、それを知っているのが良心です。人が悪い思いを抱き、悪い行動する時に、「それで本当にいいのか」とささやく良心の声があります。そこで良心の葛藤が生じてきます。
「新約聖書ギリシャ語小辞典」において、シュネイデーシスは、「善悪を見分ける生得的能力、自分の行ったことを心の中で無言のうちに証し続ける意識」と説明されています。
例えば、ローマ人への手紙2章15節には、ユダヤ人には律法が与えられているが、異邦人には「良心」が与えられているとして、「彼ら「異邦人)は律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証ししていて、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明しあったりするのです。」とあります。良心は、「神が人に与えた番人(watchman)なのです。ただこの良心は麻痺したり、鈍化することもあります。テモテ第1の手紙では、「良心が麻痺した、偽りを語るものたちの偽善」(Ⅰテモテ4:2)と記されてあります。またパウロは「邪悪な良心」(ヘブル書10:22)に対して「健全な良心」(1テモテ1;5、1ペテロ3:21)を強調しています。
「生得の良心と聖霊に導かれた良心」
「生得の良心」は麻痺しやすいものですが、聖霊に導かれた良心は鋭く、神への奉仕へ導くものです。ヘブル書9:14には、「キリストが傷のないご自分を、とこしえの御霊によって神にお献げになったその血は、どれだけ私達の良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕える者にすることでしょうか。」とあります。したがって、単に「生得の良心」のみならず、聖霊によって聖別され、敏感にされた良心こそ、聖書の示す良心の働きであると言えます。「生得の良心」は逸脱したり、鈍感になったり、善を悪と取り違えたり、間違いやすいものです。パウロは、ローマ人の手紙9:1~2節で、「私の良心も、聖霊によって私に対して証ししていますが、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります」と同胞ユダヤ人に対する救霊の思いを告白しています。これは、聖霊によって導かれ、強められた良心です。パウロが使っている「良心」は、ローマ書2:15節に異邦人について語られる「生得の良心」を除けば、ほとんどの場合聖霊によって聖められ、強められた良心です。ある聖書注解者は、「良心は、神への義務に関して人間のこころにおける聖霊の証しである」と説明しています。一言で言えば、聖書における良心は、信仰の良心であり、神との交わりから生まれてくるのものです。