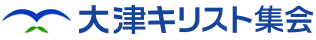トルストイ(1828-1910)と聖書(2)『復活』
「カチューシャの唄」
トルストイの小説では、女性の主人公が生き生きと描かれています。『戦争と平和』のナターシャ、『アンナ・カレーニナ』のアンナ、そして「復活』のカチューシャです。その中で最も悲劇的な女性が、鉄道の列車に身を投げたアンナ・カレーニナで、 最も希望に燃えた女性が、囚人としてシベリア送りになるカチューシャです。
トルストイの『復活』は、大正時代島村抱月(1871-1918) が、1918年芸術座で、日本版「復活」を公演し、カチューシャ役の松井須磨子(1886-1919)が「カチューシャの唄」を歌ったことによって、全国的にヒットしました。この歌の作詞は、島村抱月と相馬御風、作曲は中山晋平でした。
ちなみに島村抱月は1918年スペイン風邪にかかり死去しますが、須磨子は同年二ヶ月後抱月を追って自殺しています。
「復活のメッセージ」
『復活』(1910年)は、当時のロシアの政治・社会批判と同時に、主人公ネフリュードフの魂の変遷を主題とするトルストイの晩年(70歳の時)の書物です。この書物では、ロシアのツアー体制下における官僚制度の批判、農奴解放、そして革命運動の動きがリアルに描かれています。大土地所有者で貴族であったトルストイが、農奴解放に積極的であり、ツアー体制に批判的で、農民や革命運動にシンパシーを感じていたことがわかります。
同時に、本書は、主人公のネフリュードフの回心の軌跡、つまり堕落した魂の復活の記録でもあります。彼は、この世の習慣や価値観に流されていく人生に決別し、道徳的・倫理的に誠実に生きようとし、隣人愛を実践しようとします。その志は、人間関係の変化に限定されず、間接的に非道で抑圧的な体制の変革に繋がっていくものでした。
トルストイは、彼の分身で、『復活』の主人公であるネフリュードフについて、「彼は、道徳的のための犠牲が最高の精神的な喜びになるタイプの人間であったので、土地私有権を行使しないことに決め、すぐに父の遺産として彼のものになっていた土地を農民に譲り渡してしまっていた。」(①-12)と述べています。
「ネフリードフの内面的な戦い」
主人公ネフリードフは、当初は誠実で自己犠牲的な青年でしたが、ある時から自分の快楽を求める堕落したエゴイストに変質していきます。正確に言うと、二つの性質がネフリードフの心の中で戦い合っていましたが、後者の方が優勢になり、前者を圧倒していきます。この点に関して、トルストイは以下のように述べています。
「誰でもそうなのだが、ネフリードフの内部には二人の人間がいた。一人は、他人のためにも幸福となるような幸福しか自分に求めない精神的な人間であり、もう一人は自分のためにだけ幸福を追求して、その幸福のためには全世界の幸福を犠牲にすることも平気な動物的な人間であった。ペテルブルグと軍隊の生活がネフリードフの中に生み出した、この狂気じみたエゴイズムの時期には、彼の内面に動物的な人間が君臨し、精神的人間を完全に圧殺してしまっていた。しかし、カチューシャに会い、三年前に彼女に感じたものを再び味わった時に、精神的な人間が頭をもたげ、その権利を主張し始めた。そしてネフリードフの中では、彼自身意識しない内面的な戦いが進んでいた。」(①-14)
「ネフリードフの復活の転機」
ネフリードフの転機は、彼が殺人事件の陪審員で出廷した時、被告として裁かれていた人物がなんと彼が以前愛して、子どもを孕ませ、捨ててしまったカチューシャ本人であることに気づいたことにありました。その後カチューシャはネフリードフに捨てられたことをきっかけに、売春婦に堕落し、自暴自棄の生活を送り、冤罪で殺人の罪を着せられ起訴されていたのです。ネフリードフは、法廷でカチューシャに会い、カチューシャの人生を狂わしたことに罪責感を覚え、カチューシャを愛し、結婚しようと涙ぐましい努力をします。彼は、自己中心的なエゴイズムを克服し、カチューシャのために、また権力によって虐げられた社会的弱者や政治犯のために尽くす道を選び取ります。
もちろんネフリードフにとって、12年間の堕落したエゴイストの生活から立ち直ることは容易ではありませんでした。まさに「出口なし」の状態です。しかし、彼は、新たな決意をして、立ち上がります。この時の彼の心の状態は以下のように描かれています。
「その距離があまりにも大きく、汚れがあまりにもひどかったので、彼は最初、掃除は不可能だと絶望したほどだった。もう自己完成や向上などは試してみた、そして何の成果もなかったではないかと心の中で誘惑者の声が言った。——しかし自由な精神的存在がすでにネフリードフの中で目覚めていた。——どんな代償を払っても、おれをしばりつけているこの虚偽をたちきってやる。そしてなにもかも打ち明け、みんなに本当のことを言い、本当のことをするのだ。」
そして彼は、「主よ、我を助け、我を導きたまえ。来たりて、わが胸に宿り、もろもろの汚れより、我を清め給え!」と祈り、神の助けを求めています。
しかし、彼は、神の力に信頼し、神によって変えられていくのではなくて、自分の中に存在している善の力、自分の中に内在する神を感じます。つまり、「ネフリードフは、自分がその神だと感じ、——すべてのこと、人間が出来る限りも最も良いすべてのことを、自分は今することができる」と確信するのです。
「シベリア行き」
そしてネフリードフは、カチューシャに自分の罪を告白し、結婚することによって、自分の罪を償うことを決意し、有罪判決を受け、シベリア行きを命じられたカチューシャと一緒にシベリアへ赴きます。当初カチューシャは、ネフリードフの行為に不審感を持ち、「あんたは、あたしをこの世で慰めものにしておいて、同じあたしをだしに使って、あの世で救われたいのさ! いやらしいよ。あんたなんか。あんたに眼鏡も、脂ぎった胸くしの悪いその面も、帰れ、帰っちまえ」(①-59) とあしらっていました。しかし、カチューシャの心もネフリードフの献身的な行為によって、変化していき、ネフリードフを心から愛するようになります。こうした彼女の変化を見て、ネフリードフは「そうだ、そうだ、彼女はもうすっかり別の人間だ。」「愛は何者にも打ち負かされない」という思いを抱くに至ります。そして彼は自分とカチューシャの変化だけではなく、愛の広がりによって、周りの人々や社会が変化していくことを期待します。
「山上の垂訓」
トルストイにとっての行動の基準は、新約聖書の福音書でイエスが語られた山上の垂訓でした。彼は『復活』において、「人間に許される最高の幸せー地上の神の王国」を達成し、暴力を根絶するために五つの戒律の遵守を求めています。
第一は、「殺してはならない」で、これはトルストイの非戦論・非暴力主義、死刑廃止に繋がっていきます。第二は「姦淫してはならない」という貞節、第三は「誓ってはならない」第四は「一方のほおを打たれたら、他方のほおを差し出す」という無抵抗の精神、そして第五は、敵をも愛すべしと言う命令です。第四と第五の戒律こそ、トルストイが追求した実践的な愛でした。
『復活』の最後は、「神の国と神の義とを求めよ」という聖書のことばが引用され、「これこそがおれの一生の仕事だ。この世から、ネフリードフにとって全く新しい生活が始まった。——ネフリードフの人生のこの新しい時期がどんなかたちで終わるか、それは未来が示してくれる。」(③-28)という意味深長な文章で終わっています。
「トルストイの結末」
トルストイは、福音書の倫理を全うし、最後まで愛の実践を行うことができたでしょうか。彼には、そうしようと思っても出来ない自分に対する葛藤はなかったでしょうか。使徒パウロがローマ書7章で書いたように「私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています」(7:19)と告白し、「私は本当にみじめな人間です。」と叫んだ苦しみはなかったのでしょうか。
トルストイは、1903年1月6日日記において、「私は地獄の苦しみを感じる。私は過去の卑劣さを思い出す。その思いは私念頭から離れず、私の一生を暗いものにしている。普通人は死後までこも世の思い出を持って行けないことを残念がる。けれどもそうであることはなんと幸せだろう。もしあの世に行っても私がこの世で犯した罪をすべて覚えているとしたら、何という苦しみであろう。」 と慨嘆しているのです。
こう述べつつも、彼は自分の醜さを認めて、神に赦しを求めようとせず、自分の力で、愛の実践を行おうと努力します。彼は、聖書を通して、イエス・キリストの十字架による罪の赦しがあることを知っていました。しかし彼はその道を意識的に拒絶します。
「キリストの贖いに対するトルストイの態度」
トルストイは、自分の善行と愛の実践によって自己変革を追求しましたが、キリストの十字架と復活が、聖書の主要なメッセージであることをも理解していました。したがって彼の書物では、キリストの十字架の贖いがしばしば話題として登場します。
『復活』では、神の前における罪の悔い改めと、キリストの十字架の贖いを語る二人の人物が登場します。二人とも外国人、つまりよそ者という設定です。しかし、トルストイの彼らに対する評価は、どこか冷淡で批判的で、戯画的です。一人は、贖罪信仰をキリスト教本質と考えるチャールスキー伯爵夫人の集会で英語で福音を語っていた外国人説教者キゼウエテルです。
彼は、人間の罪と神の裁きからどのように救われるかを説き、「だが救いはあります。よろこばしい救いが。その救いとは、わたしどものために一身を、苦難に捧げられた神のひとり子が、わたしどものためにお流しになった血なのであります。みなさん、ひとり子を人類の身代わりとして贖罪におささげになった神に感謝しようではありませんか。」(②-17)と語ります。
もう一人は、イギリス人で、囚人に対して福音書を配布していますが、ネフリードフに対して、「キリストは彼らをあわれみ、愛しておられたと言ってやってください。——。そして彼らのために死んだのです。もし、彼らがそれを信じれば、救われるのです。この本にはそういうことが全部書いてある。」と語りますが、ネフリードフは関心を示しません。
「トルストイとドストエフスキー」
トルストイのキリスト教は、キリストなきキリスト教です。トルストイがイエス・キリストについて熱っぽく語っているところはありませんし、イエスは単なる人間にしか過ぎませんでした。それに対してドフトエフスキーは、イエス・キリストに惹かれ、「もし誰かが自分にキリストが真理の埒外に立っていることを示し、またもし真理が、本当にキリストのほかにあるならば、僕は真理のところに留まるよりも、キリストのところに留まる方が良い」とさえ断言しています。
キリストの贖罪ーイエス・キリストの十字架による罪の赦しーは、トルストイにとって問題になりませんでしたが、ドストエフスキーにとっては、それこそがいのちそのものでした。彼が『カラマーゾフの兄弟』の冒頭で示したイエスのことば、つまりイエス御自身の十字架の死を予告することばが、そのことを如実に示しています。
「まことに、まことに、あなたがたに言います。一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままです。しかし、死ぬなら、豊かな実を結びます。」(ヨハネの福音書12:24)
参考文献
トルストイ 『復活』(上)(下)(岩波文庫、2020年)
ロマン・ロラン『トルストイの生涯』(岩波文庫、1996年)
清水氾『不死へのいざない』(KGK 新書、1968年)