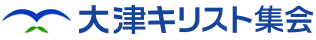トルストイ(1828-1910)と聖書(1)
『イワン・イリッチの死』―死の恐れとの闘い

「 ある中学生の投書」
朝日新聞(2022年2月7日)の声の欄に、13歳の女子中学生の投書が掲載されており、読んで釘付けになりました。このような若い少女でさえも、死の問題を真剣に考えていることに驚いたのです。一部抜粋します。「死んだら、どうなるんだろう。わたしはよく、そんなことを考える。天国や地獄という死後の世界が本当にあって、そこで存在し続けることができるのなら、そう願いたい。けれども、死によって私の意識も、心も、何ものかが永遠に消え失せてしまうとしたら—–いま、これを書きながらも私は、底なし沼に沈んで行くような恐怖に襲われている。そして、『まだ私は若いから』と思考を中断するのだ。他の人はどうだろう。私が敏感なのかと思ったが、まわりの友人に聞いてみるとやは り、恐ろしくて考えるのをやめるという。この恐怖からどうやって逃げたらいいんだろう。大人になったら、怖くなくなるのだろうか。」
「トルストイと死の問題」
ドストエフスキーと双璧をなすロシアの文豪トルストイの生涯は死の恐怖と不安に苛まされた人生でした。彼の大作『戦争と平和』(1863-1869年)や『アンナ・カレニーナ』(1873-1877年)においても彼の死の描写は際立っています。トルストイ自身が三歳の時に母を、九歳の時に父を、十歳の時に祖母を、そして十三歳の時に後見人の叔母をなくしています。特に母の死によって、彼は絶望を経験します。それ以来、彼は、死によってすべてのものがガタガタと音を立てて崩れていくという虚無感にとらわれます。『アンナ・カレニーナ』では、兄ニコライの死が近づいていることについてのレーヴィンの思いが綴られています。レーヴィンはアンナと共に『アンナ・カレニーナ』の主人公で、トルストイの分身といってもいい存在です。「兄の姿と死の接近とは、レーヴィンの心に——ふと襲われたあの恐怖感をよみがえらせた。それは死というものの不可解さ、と同時にその接近や避けがたさに対する恐怖であった。」(『アンナ・カレニーナ』第5篇19)
彼は、「私の行く手に待ちかまえているあの避け難い死によって滅せられない悠久の意義が私の生活の中に、あるだろうか」と自問自答しています。トルストイにとって死を超えた希望がない限り、すべてのことがむなしく思えたのです。そのような虚無感が、彼の人生を蝕みます。結婚してしあわせな家庭生活を送っている時も、文豪として名声を博している時も、虚無感によって彼の心は苛まされるのです。
彼は五十歳の時に新しい生涯を歩むことを決意する思いで書いた『懺悔』(1978-1882)においても、以下のように述べています。
- 「人生は無意味なものである。ーこれが真理であった。まるで、あくせくと人生の道を歩い たあげく、深淵に達したもののようであった。そして私は、自分の前に、滅亡の他何ものもないことを発見したのである。しかも、私は、止まる事もできなければうしろに引き返すこともできず、また自分の行く手に苦悩と真の死ほか、つまり、完全な絶望の他、何ものもないという事実を見ずにすむよう、眼をおおうこともできなかった。」(『懺悔』(四))
「イワン・イリッチの死」
しかしなんといってもトルストイが、最も死の真相に肉薄し、リアルに描いたのは、「イワン・イリッチの死』(1882年)です。この書物は多くの哲学者や文学者にも甚大な影響を及ぼしました。この書物から、トルストイの死についての考えを紹介します。
イワン・イリッチは、中央裁判所の判事で、資産家であり、妻と二人の子供がいました。トルストイは、この死をまじかに迎えるイワンの苦しみを4点に亘って描いています。一言で言えば肉体的・精神的・霊的(宗教的)な苦悶です。
第1点は、イワンは、肉体的な苦しみがひどく、時にはアヘンを服用せざるえませんでした。痛みがコントロールされることが、平安な最後を迎えるに必要な条件です。
第2点は、彼は家庭で闘病生活を送りましたが、奥さんや娘に憎悪に近い感情を持っており、精神的な支えがなく、孤独でした。死が近くても、奥さんや家族の愛によって支えられている死とは全く異なります。家庭的な不和は、死を受容するに際して大きな障害となります。
第3点は、医者も家族もイワンに病気の真相を告げなかったので、イワンは自分が虚偽の中に生きていることを憂えました。現在は、日本でも、最終ステージにある癌でも本人に告知されるようになりましたが、以前は、例えば胃がんでも胃潰瘍と偽わりの告知がされていて、患者は死に対する心の準備をすることはできませんでした。この点、トルストイは、以下のように記しています。
- 「イワン・イリッチの主な苦しみは嘘であった。——たとえどんな事をしてみても、さらに悩ましい苦痛と死のほかには、結局、どうもなりようはないのである。この偽りが彼を苦しめた。すべての人が、自分を知っていれば病人も知っていることを認めずに、この恐ろしい状態を嘘でごまかそうとするばかりか、彼自身にまでこの偽りの仲間入りをさせようとしている——この事実が彼を苦しめるのであった。虚偽、虚偽、彼の死の前夜に行われている虚偽!」(七).
第4点は、宗教的煩悶です。この苦しみには二段階あります。第一段階は、なぜ自分がこのような死に至る不治の病を受けなければならないかという疑問で、それは神を呪ることにも発展します。
「彼は、自分の頼りなさを思い、人間の残酷さを思い、神の残酷さを思い、神の存在しないことを思って泣いた。『なぜあなたはこんな事をなすったのです?なぜ私をここへ連れて来たのです? なんだってこんなに恐ろしいいじめかたをするのです。——しかし一体なんの罰です?一体わたしが 何をしたというのです?なんのためです。」(九)
第2段階は、そこから進んで、自分の今までの生涯を見つめ直す段階です。ここにおいても最初は、裁判官である神に対して自分が被告して裁かれることを想定して、「おれは何も罪はないのだ!」と毒々しく叫びます。しかし次第に彼の心には、「今まで送ってきた生活が、【神の】掟に外れた間違ったものだという疑念が沸き上がって」きます。イリッチはその思いを以下のように述べています。
- 「勤務も、生活の営みも、家庭も、社交や勤務上の興味もすべて間違いだったかもしれない。彼は、これらのものを自分自身にむかって弁護しようと試みた。しかし突然、自分の弁護しているものの脆弱さを痛切に感じた。それに、弁護すべきものすら何もなかった。」 (十一)
それでは、イワン・イリッチは、最後にどのように死んでいったのでしょうか。トルスト イは、そしてトルストイの分身であるイワン・イリッチは、死の恐れを克服しえたでしょうか。実はイワンは、死の寸前に光明を見ています。
- 「『ところで、死は? どこにいるのだ?』古くからなじみになっている死の恐怖を探したが、見つからなかった。いったいどこにいるのだ。死とはなんだ。恐怖はまるでなかった。なぜなら死がなかったからである。死の代わりに光があった。『ああ、そうだったのか!』彼は声にたてて言った。『なんという喜びであろう』」(十二)
死の寸前、死がなくなったとはどういう意味でしょうか?また死を迎えることを、「なんという喜びである」となぜ言えるのでしょうか?その理由については何も記されていません。イリッチは、そしてトルストイは真に死を克服することができたのでしょうか?この問いに対して、清水氾は、『不死へのいざない』において、彼が死を克服したことを否定します。それは、トルストイが晩年の大作である『復活』において、トルストイの分身であるネフリュードフが、親しかったクルイリツォフが死んだ時に、次のように自分の思いを吐露しているからです。
「愛すべきクルイリツォフまで破滅させたあのすべての悪が勝ち誇り、君臨し、それを打ち負かす方法を突きとめる見込みさえ全く見当たらないのだった。」(『復活』第3編28)
「 死に対する聖書のメッセージ」
ここで聖書の死についての記事を紹介します。聖書は死で全てが終わると語ってはいません。逆に、神に罪赦され、永遠の命を与えられた者は、天国においてキリスト に迎えられると語ります。肉体的な死は、天国に至る門にすぎません。イエスは、処刑される前にイエスを信じた強盗に対して、はっきりと「今日、あなたは私と共にパラダイス[天国]にいます」と約束されました。
また使徒パウロは、「肉体を離れて、主の みもとに住む方が良いと思っています。そういうわけで、肉体を住まいとしても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは、主に喜ばれることです。」(IIコリント5:8) と語っています。
天の御国に受け入れられる人は、イエス・キリストが十字架で流された血潮によって罪赦され、永遠の命を与えられた人です。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかり、三日後に墓を打ち破ってよみがえられた方であることを信じる全ての人は、天国に凱旋し、罪と死に勝利することができます。聖書はイエス・キリストの復活の結果として、死と罪に対する勝利が実現したことを高らかに宣言しています。
「死は勝利に飲まれた。死よ、おまえのとげはどこにあるのか。死ののとげは罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。」( 1コリント15:54-57)
そして聖書は、イエスが、肉体をとってこの地上にこられた目的を、「死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分 の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷として繋がれていた人々を解放するためでした。」(ヘブル書2:14-15) と述べています。これこそ、最初に紹介した一人の女子中学生の真摯な問いに対する、聖書の回答なのです。
「トルストイの誤った選択」
残念ながら、トルストイは、死を超えた永遠のいのちの希望、天においてキリストに迎えられるという希望を持ってはいませんでした。トルストイの分身であるイワンは、『イワン・イリッチの死』において、自分の生涯が神の前に間違っていたのではないかと思うようになりました。その気づきは、大事なことです。しかし、彼は、良い行いを積み重ねることによって、過去の間違いを償い、神に受け入れられようとしました。しかし、彼は、イエス・十字架の贖罪も、復活も否定しました。彼の信仰とは、神の掟を守り、神の前に良い行いを積み重ねるという逆方向の道でした。彼は、『懺悔』で、次のように語っています。
- 「私は私を創りだし、何ものかを私に望んでいる、目に見えない意志に対する信仰に立ち返った。わが生活の唯一絶対の目的は、より良き人にになるであるという自覚に、すなわち、この意思と最も融合して生きることであるという自覚にたち返った。——すなわち、神に対する、道徳的完成にたいする、人生に意義を与えている伝統に対する信仰に立ち返ったのである。」(十二)
それは、聖書の「山上の垂訓」(マタイの福音書5-7章)と呼ばれる倫理を徹底して実践することでした。一言で言うと、「自分を愛するように隣人を愛する」という愛の実践です。しかしそこには、神の光に照らされて自らの罪を自覚して、神にひれ伏すトルストイの姿は見当たりません。また救い主であるイエス・キリストに対する信仰と愛を見出すことはできません。逆に愛の実践を通して、自らの正しさを主張し、力づくで天国をもぎ取ろうとする姿勢が顕著です。彼は自らのエゴイズムを克服し、他者を愛し、道徳的に生きるために、自分の土地や財産を農民に与え、慈善事業に尽力し、死刑制度に反対し、日露戦争に反対の運動をしました。そしてロシアを初め日本においても多くのトルストイ信者を生み出しました。そのようなトルストイの活動は、彼の大作『戦争と平和』、『アンナ・カレニーナ』、『復活』と共に、多くの人々に甚大な影響を及ぼしました。そして彼は誤ってキリスト教信者として理解されるようになりました。しかし、彼の晩年は悲惨でした。妻ソフィアとの関係は破綻し、1910年10月八十二歳の高齢の時に、家出し、駅で病気を発症し、孤独のうちに死に飲みこまれれてしまいます。彼はなくなる時に、イワンが叫んだように、「何という喜びであろう」と言うことができたでしょうか?
「信仰義認と行為義認」
一体トルストイのどこに問題があったのでしょうか?彼は真剣に生き、人生の生きがいを求め、死にうち勝つ道を必死で 追求しました。その点については、敬意を表するものです。しかし、トルストイは自分の立派な行いによって、下から神に近づき、神に受け入れられ、天国に入ろうとしました。それは、良い行いをすることによって、罪の清算を求める「行為義認」の道です。 しかし聖書が語る救いは、神を見上げ、私たちの罪を負って十字架にかかり、三日目に墓を打ち破って復活された神の御子イエス・キリストを信じる「信仰義認」の道です。パウロは、このことについて、次のように記しています。最後に聖書から引用いたします。
「全ての人は罪を犯したので、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリスト・イエスの贖いを通して、価なしに義と認められるのです。」(ローマ書3:23-24)
冒頭で紹介した女子中学生の問いは私たちの問いでもあります。是非、聖書のメッセージに耳を傾けてくださるようお勧めします。
参考文献
トルストイ『アンナ・カレニーナ』(上)( 中)(下)(中村融訳、2014年)
トルストイ『懺悔』(原久一郎訳、岩波文庫、2013年)
トルストイ『イワン・イリッチの生涯』(米川正夫訳、 2020年)
トルストイ『復活』(上)(下)((藤沼貴訳、岩波文庫、2014年)
清水氾『不死へのいざない』(KJK新書、1968年)