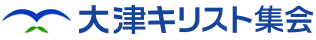森鴎外(1862ー1923)と聖書
ーかのようにの生き方ー
「森鴎外のプロフィール」
鷗外は、1862年、現在の島根県津和野に、医者である父静男と母峰子の長男として生まれます。本名は林太郎です。1881年、東京大学医学部を卒業し、陸軍に軍医として迎えられ、1884年から1888年までの約4年間、ドイツのライプツィヒ、ドレスデン、ミュンヘン、そして最後にベルリンで医学や衛生学を勉強します。1889年に赤松登志子と結婚,長男 於菟(おと)がうまれ、翌年離婚、1902年に荒木志げと再婚、長女茉莉(まり)、次女杏奴(あんぬ)、次男 律が生まれています。1907年に鷗外は、陸軍軍医総監、陸軍省医務局長という陸軍軍医の最高の地位に登りつめています。彼は、1922年7月に死去し、遺骨は三鷹の禅林寺の墓に納められています。私は大学時代、東京の三鷹市の下連雀に住んでいた時、禅林寺に行き、森林太郎の墓石を何度か見に行ったことがあります。
鷗外の小説としては、『舞姫』(1890年)、『青年』(1910年)、『妄想』(1911年)、『かのやうに』(1912年)、『大塩平八郎』(1914年)、『高瀬舟』(1918年)などがあります。ここでは、特に『かのやうに』と『妄想』を取り上げ、森鷗外の思想に迫ることとします。
「かのようにの哲学」
鷗外は、ドイツ留学中にマックス・シュティルナー(1806-1856)やアルトゥル・ショペンハウアー(1788-1860)などの厭世哲学、虚無主義に触れます。彼は『妄想』で、「多くの師に逢ったが、1人の主には逢わなかった」と述べています。主とは、キリスト教的用語で、神ないしキリストで絶対的な存在を意味します。鷗外の価値観は相対主義的で、確固とした立場があるわけではありません。確かな価値観や世界観がなければ、「すべてが虚しい」のですが、鷗外はその虚無主義を徹底させないで、ドイツの哲学者ファイヒンガー(1852〜1933)の「かのようにの哲学」に自己の生き方の支えを見出します。つまり、もはや確固たる価値は存在しないけれども、あたかも存在するかのように生きていくという生き方です。そして鷗外の場合、それは日本の家父長制や天皇制的な日本の保守的な伝統であり、陸軍軍医としての官僚的な生き方でした。彼の生き方の基本は、彼の短編『かのやうに』(1912年)に余すところなく、示されています。いわば、自分の本当の姿を隠し、仮面をつけて生きる生き方です。
「大逆事件のインパクト」
「かのやうに」は、1912年に、山形有朋(1838-1922)から危険思想対策としての提案を求められて書き記したものです。1910年に 大逆事件が発生し、明治天皇暗殺を計画したとして、幸徳秋水(1871-1911)初め、無政府主義者や社会主義者が大量に検挙され、12名が処刑されました。鷗外は、明治の天皇制国家における権威の衰退に危機感を覚えざるを得ませんでした。
この短編では、鷗外の分身は、主人公の五條子爵の息子秀麿です。秀麿は、ファイヒンガーの「かのようにの哲学」に自分のよって立つ立場を見出しています。
秀麿は、最初に道徳的・政治的価値の相対性を論証します。しかし彼は、いかなる価値も絶対ではないとしても、社会がなんらかの価値体系を必要としている以上、伝統的な真理や慣習が絶対的な真理である「かのように」振る舞うしかないと考えました。日本の国体は、「天孫降臨」と「万世一系の天皇」という古代の記紀神話(古事記と日本書紀)に立脚しています。秀麿は、それが歴史的事実ではなく神話であることを知りつつも、あたかも事実であるかのように振る舞うのです。この点、鷗外は以下のように述べています。
「秀麿がためには、神話が歴史でないということを言明することは、良心の命じるところである。それを言明しても、果物が堅実な核を蔵しているように、神話の包んでいる重要なものは、保護して行かれると思っている。彼を承認しておいて、此れを維持して行くのが、学者の務めだと云うばかりではなく、人間の務めだと思っている。」(『かのやうに』)
これに対して父親の子爵は、秀麿と異なり、神話が歴史でないと言明することは、「人生の重大なものの一角が崩れ始めて、船底の穴から水の這入るように物質的思想が這入って来て、船を沈没させずにはおかない」と危険視するのです。
父親の子爵にとって、記紀神話は天皇制国家の存立にためには不可欠でしたが、秀麿は、それが事実でないとしても、あたかも事実であるように尊重するのです。ちなみに、子爵のモデルは、鷗外と親交があった山縣有朋(1838-1922)と言われています。
秀麿にとって、こうした「かのように」の振る舞いは、国家や社会の領域のみならず、宗教の領域においても同様でした。
鷗外は、4年間のドイツ留学時代に、哲学やキリスト教にも深い関心を示しました。鷗外は、たとえ神の存在を事実として信じられないとしても、宗教の必要性を認めており、秀麿に、次のように言わせています。
「かのやうにがなくては学問もなければ、芸術もない。宗教もない。人生のあらゆる価値のあるものは、かのようにを中心としている。昔の人が人格のある単数の神や、複数の神の存在を信じて、その前に頭をかがめたように、僕はかのようにの前に敬虔に頭を屈める。—–神が事実ではない。義務が事実ではない。これはどうしても今日になって認めずにはいられないが、それを認めたのを手柄にして神をけがす。義務を蹂躙する。そこに危険は始て生じる。行為はもちろん、思想まで、そう云う 危険なことは十分に撲滅しようとするが好い。しかしそんな奴の出てきたのを見て、天国を信じる昔に戻そう。地球が動かずにいて、太陽が巡回していると思い昔にもどそうとしたって、それは不可能だ。——どうしてもかのようにを尊敬する。僕の立場より外に、立場はない。」( 『かのやうに』)
また鷗外は、同じく五条秀丸を主人公とする短篇「吃逆」(しゃっくり、1912年)を書いています。そこでは、ベルリンから帰国した秀麿の友人幣原が、哲学者ルドルフ・オイケン(1846〜1926)について秀麿に語っていることが記されています。オイケンに、鷗外のキリスト教理解が投影されているように思われます。オイケンの考えは、もはやキリスト信仰は信じるにたりないが、宗教なしでは人間は生きていけないというものでした。
「神が歴史のある時期に人間の形を現したということは、学問上ばかりではなく、現代人の思想には一般に容れられないと云っています。それか原罪とか贖罪とか云う思想もそうで。人間の罪を神が怒って、自分の子の血で贖はせると云うことは、現代人には想像せられない。それからキリストが神と人間とのあいだに、紹介者のようになって立っていると云うことも、現代人は却って迷惑に思うと云っています。そのくらいですから——永遠に動かない真理として聖書を立てておくことに同意するはずもないと云っています。それですから、クリスト教維持となのってはいるようなものの、詰まり宗教維持と広く云っても好いことになるでしょう。」(「吃逆」)
このことばの中に聖書の基本的な教理がはっきりと示されています。神が人となられたという受肉、人間は生まれながらにして原罪を持っていること、その罪をイエス・キリストが代わりに身に負い、十字架の死によって贖われたこと、そしてキリストが、神と人間の仲介として和解を成し遂げてくださったこと、聖書が永遠に動かない真理であるという正統的な信仰の教義が否定的ですが示されています。オイケンや鷗外にはもはや信じられない教義でしたが、ここでは鷗外が正統的な信仰の教義を正しく理解していたことに注目したいと思います。それこそが、聖書の福音の重要なメッセージでした。
「妄想」
もはや事実として信じていないものを、そうであるかのように行動する「かのようにの哲学」は、人間に建前と本音という心の分裂をもたらします。まさに日本人的な生き方かもしれません。
「かのようにの哲学」は、絶対的なものは存在しないという懐疑主義を前提としています。彼のニヒリズム(虚無主義)は、ドイツの哲学の影響もありましたが、根本的には死に対する恐れに発しています。鷗外は、1911年に親しかった乃木大将が自殺したことに衝撃を受け、同年『妄想』を発表します。これは、当時49歳になっていた鷗外の思想史的自伝ですが、別荘の主人が、自分の過去を振りかえるという構成になっています。そして、死の問題から始まっています。
「朝凪の浦の静かな、鈍い、重苦しい波の音が、天地の脈拍のように聞こえてくるばかりである。——それを見て、主人は時間というものを考える。生ということを考える。死ということを考える。——しかし、死というものは、生というものを考えずには考えられない。死を考えるというのは、生がなくなると考えることである。」(『妄想』)
「仮面を付けての演技」
「妄想」における主人は、過去を振り返りながら、自分の人生が仮面を被って演技しているようなものだと吐露しています。
「生まれてから今日まで、自分は何をしているのか。始終何物かに鞭うたれ駆られているように学問ということにあくせくしている。—–しかし、自分のしていることは、役者が舞台へ出てある役を勤めているに過ぎないように感ぜられる。むち打たれ駆られているばかりいるために、その何物かが醒覚する暇がないように感ぜられる。勉強する子供から、勉強する学校生徒、勉強する官吏、勉強する留学生というのがその役である。赤く黒く塗られている顔をいつか洗って、一寸舞台から降りて、静かに自分というものを考えて見たい、背後の何物かの面目を覗いて見たいと思い思いしながら、舞台監督の鞭を背中に受けて、役から役を勤めあげている。この役が即ち生だとは考えられない。背後にあるあるものが真の生ではあるまいかと思われる。」(『妄想』)
演技者としての生ではなく、その背後にある「真の生」とは鷗外にとっては、何なのでしょうか。彼は、真の生、真のいきがい、真の自己を見出すことができませんでした。そこに鷗外の悲劇があります。
「自分は永遠の不平家である。どうしても自分のいない筈のところに、自分がいるようである。どうしても灰色のとりを青いとりに見ることはできないのである。道に迷っているのである。夢を見ているのである。夢を見ていて、青い鳥を夢 のうちに尋ねているのである。——-自分はこのままで人生の下り坂を下っていく、そしてその下りはてたところが死だということを知っている。しかし、その死はこわくない。人の説に、老年になるに従って増長するという『死の恐怖』が自分にはない。——死を恐れをせず、死に憧れもせずに、自分は人生の下り坂を下っていく。」(『妄想』)
鷗外にとって苦痛であったのは、死そのものではなく、「真の生」を見出しないままに人生を終えてしまうことでした。「青い鳥」を見いだし得ない、永遠の不平家で終わることでした。しかし、鷗外はは「真の生」を徹底して追求せず、「かのようにの哲学」に身を委ねてしまうのです。
ところで、鷗外にとって死とは自我の消滅ですが、ほんとうに、鷗外は死がこわくなかったのでしょうか。死をこわがってはならないという武士道の伝統が強く、あたかも死がこわくないかのように、演技をしていたのではないでしょうか。
この点に関して加藤周一(1919-2008)は、『日本人の死生観』(上)において、「死に向かっての鷗外のうわべには平静な態度は、彼のデスマスクにもきわめてはっきりと現れている。しかし実のところそれは、鷗外が生き抜いた深い葛藤と苦痛の歴史をおおうヴェールにすぎない」と、鷗外の心の奥底にある死に対する恐怖を描き出しています。
「鷗外の遺言」
鷗外は1923年7月9日に、肺結核で死去しました。享年60歳です。臨終の前夜、突如として、太くて高い大声を出し、「馬鹿らしい、馬鹿らしい」と叫んで、静かに眠ったと伝えられています。「馬鹿らしい」が何を意味しているか定かではありませんが、「かのように」の仮面を被った演技に対する自己評価ではないでしょうか。
鷗外の生涯を知る上で大事なことは彼の遺言です。彼は、次のように言っています。
「遺言 死は一切を打ち切る重大事件なり、如何なる官権威力といえども、これに反抗することを得ずと信ず。余は、石見人森林太郎として死せんと欲す。宮内省、陸軍省のあらゆる外形的取り扱いを辞する。」
この遺言には、鷗外が墓石に一切の位階の称号を彫ることを禁じることによって、60年の間築き上げてきた「かのように」の仮面の生き方を捨て、裸になって、真の自己に立ちもどろうとする願いがあります。ちなみに、鷗外は1907年45歳の時に陸軍軍医総監、陸軍章医務局長の要職の地位にありました。陸軍軍医としての名声や地位のみならず、鷗外という名も残さず、文豪としての業績や評価も一切捨て去って、いわばあらゆる仮面を脱ぎ捨てて、一人の人間として死すという遺言です。
鷗外には、二重の仮面がありました。第一の仮面は、軍医や家長としての伝統的に定まった生き方では満たされない思いを文学や小説に注ぎ込んでいたことです。第二は、内面の世界に没入する文学者や小説家としての顔も仮面であったと言えます。小説や文学の世界も虚構の世界であり、真の生とはいえないものでした。 鷗外自身、「小説は、事実を本当にするという意味においては、嘘だ」と述べています。この意味において真の自己に立ち返るためには、文豪の代名詞である鷗外という名前も捨て去る必要があったのではないでしょうか。彼は死に際しては裸の自分を凝視することを余儀なくされます。
「鷗外と聖書」
鷗外は、中国語の漢訳聖書 を精読していました。東京大学図書館の鷗外文庫には、聖書の和訳1冊、ドイツ語訳、英語訳 の聖書が保管されてあります。彼の所持していたドイツ語の家庭用聖書では、「主のために、すべての人間の立てた制度に従いなさい」(一ペテロ2:13)の聖句に下線が引かれています。というのも、権威の喪失がもがらす国家の危機ついて度々語る鷗外にとって、権威の再興は大事な問題関心でありました。そうした問題意識が権威の尊重についての聖書の箇所に 着目した理由でした。
彼がキリストについて触れた唯一の論稿は、1921年11月から1922年7月まで『明星』に書いた「古い手帳から」です。そこで鷗外は、漢語訳聖書のマタイの福音書(21:23、24,)、ルカの福音書(6:20、21)、マルコの福音書10:23〜25)を引用して、「富を持つものが神の国に入るのはなんと難しいことでしょう」というイエスの富に対する警告を紹介し、イエスが狭い民族や国家の枠を超えた世界的な平等主義者であることを賞賛しています。
「キリストは、富人の貧人を虐待する世に生まれた。そしてユダヤ人の既に神の民たる思想を狭しとし、ギリシャ人とローマ人のすでに其郷国主義を小なりとするをみた。これがキリストのその宗教を世界的平等観の上に独立した所以である。キリストが社会思想史上に重要なる地位を占めていることは明らかである。」
以上のように、鷗外が聖書に触れていたことは間違いがありませんが、彼が自分の魂の救いの問題として、聖書を真剣に読んだという形跡は見当たりません。この点は夏目漱石と共通する点です。
なお鷗外は、左遷された小倉時代(1899〜1901)中に、カトリックの神父であるフランソワ・ベルトラムからフランス語を学び、神父の自宅や教会を訪れています。フランソワ神父との間に聖書や信仰の話がなされたかはわかりませんが、彼の小倉日記には、1901年12月13に、「夜ベルトランの家にて、広島研屋町に住める宣教師シヤロンCharonnと中津三の町に住める宣教師シャブドレエンChapdelaine とに逢う。」と記されています。
後に鴎外は、茉莉(まり)と杏奴(あんぬ)という二人の娘をカトリックの学校に入れています。杏奴は50歳になった1958年にカンドウ神父(1897-1955)との出会いを通してカトリック信者になっています。
「鷗外の重荷」
鷗外の人生は、一方における文豪としての名声、他方における陸軍軍医としての輝かしい地位にもかかわらず、魂の葛藤を抱えた人生でした。彼の自伝的な短編である「妄想」にはそのことが如実に示されています。ドイツ留学で知り合ったエリーゼを自分の栄達の妨げになるという思いで捨ててしまった過去、また最初に結婚した妻登志子を母親の要求によって離縁したこと、若き日から肺結核を患っていたにもかかわらず、自分や家族の将来のために一生懸命隠し続けてきた負い目がありました。かれは、「かのように」の生き方に破綻を覚え、最後になって、仮面を脱ぎ捨てて、自分本来のありのままの姿に戻ったのではないでしょうか。
しかし、鷗外は残念ながら、キリストとの出会いを経験することはありませんでした。聖書が神の霊感の書であることを信ぜず、人間の理性を超えた神の啓示と語りかけに心を閉ざした合理主義者である鷗外の悲劇です。鷗外が、人間はどこから来てどこに行くのか、死で全てが終わりなのかについて聖書と真剣に格闘する機会があったならばと思わざるをえません。鷗外が、シュティルナーやショーペンハウアーのような懐疑主義や虚無主義ではなく、永遠に動かない聖書の真理に触れていたならば、彼の人生は変わっていたでしょう。
参考文献
森鴎外 「舞姫」、「かのように」 (『阿部一族・舞姫』( 新潮文庫、2020年)
森鴎外 「妄想」( 『山椒大夫・高瀬舟』(新潮文庫、2021年)
森鴎外 『青年』(岩波文庫、2017 年)
唐木順三『森鷗外』(現代教養文庫、1958年)
小塩節『随想 森鴎外』(青娥書房、2020 年)
中島国彦『森鷗外ー学芸の散歩者』(岩波新書、2022年)
「鷗外文庫書入門画像データーベース」(東京大学附属図書館蔵、鷗外文庫)